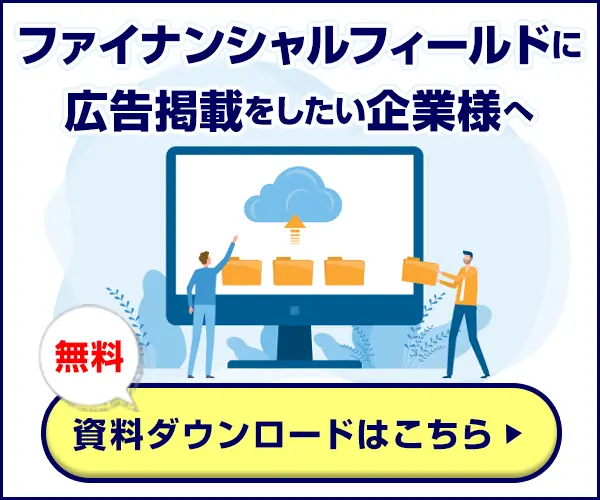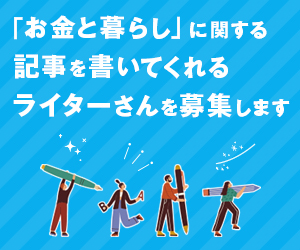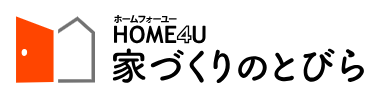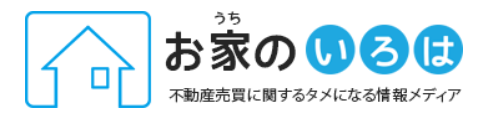そこで本記事では、贈与をするとどのような場合に税金がかかってしまうのかについてと贈与税の非課税枠について解説していきます。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
贈与税と非課税枠
贈与は、無償で自分の財産を相手に渡す意思表示をし、相手方がこれを了承すると契約が成立します。そのため、親子の間でも成立する契約です。
個人から贈与によって財産を受け取った場合は、贈与税がかかります。「子どもの将来のために」と財産を渡した場合、贈与税がかかってしまうのは避けたいところです。贈与税の課税方法は「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年贈与
1月1日からの1年間に、贈与をした財産から「基礎控除額」の110万円を引いた金額に対して贈与税がかかります。
例えば、500万円の財産を贈与した場合は110万円を引いた390万円が贈与税の対象です。贈与した財産が110万円以下であれば課税の対象にならないので、「贈与する場合は110万円以下に」抑えると良いでしょう。
相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択することもできます。相続時精算課税を選択すると、2500万円までは特別な控除を受けることができ、父母や祖父母からの贈与については限度額まで何度でも控除を受けることが可能です。
また、贈与した父母や祖父母が亡くなると、「相続財産とこれまでに受け取った贈与財産」を合算して相続税額を計算し、清算します。限度額の2500万円を超えると、「超えた部分に対して一律20%」という高い税率がかけられます。2500万円の上限額以内に抑えることができれば、特別控除を利用でき、贈与税よりも税率が低い相続税で精算できるのがメリットです。
「暦年贈与は家族以外の他人からでも可能」ですが、相続時精算課税は「60歳以上の父母もしくは祖父母からの贈与である」こと、贈与を受け取る側も「18歳以上の子や孫である」こと、といった要件があります。
また、相続時精算課税を選択すると、暦年贈与の基礎控除110万円を受けることができません。「選択する場合は申請が必要」です。
住宅取得等資金についても非課税枠がある
子が家を買う際の資金を援助した場合も贈与になります。通常であれば贈与税がかかってしまいますが、この場合も非課税枠があります。
住宅取得等資金の贈与と非課税枠
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間に父母や祖父母から住宅の購入資金などを贈与された場合、「要件」を満たすと500万円もしくは1000万円までが非課税になります。
住宅取得等資金贈与の要件
主な要件は、父母や祖父母といった「直系尊属からの贈与」であること、「贈与を受ける子や孫の年齢が18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上)である」こと、「贈与を受ける者の1年間の合計所得金額が2000万円以下である」こと、などです。
また、「一般住宅の場合は500万円」、「省エネ等住宅の場合は1000万円」が非課税の限度額になりますが、省エネ等住宅と認定されるには「要件」があります。
「断熱等性能等級が4以上」もしくは「一次エネルギー消費量等級が4以上」であること、「耐震等級が2以上」または「免震建築物」であること、「高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上」であることのいずれかに該当することの証明が必要です。
【PR】相続する土地・マンションがあなたの生活を助けるかも?
制度を理解し、うまく活用しましょう
本記事では、贈与するとどのような場合に税金がかかってしまうのか、贈与税の非課税枠について解説してきました。家族間でも贈与になってしまうので、資産を渡すことにも注意が必要です。制度の違いで非課税枠や要件が違うので、この機会に理解しておきましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国土交通省 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部