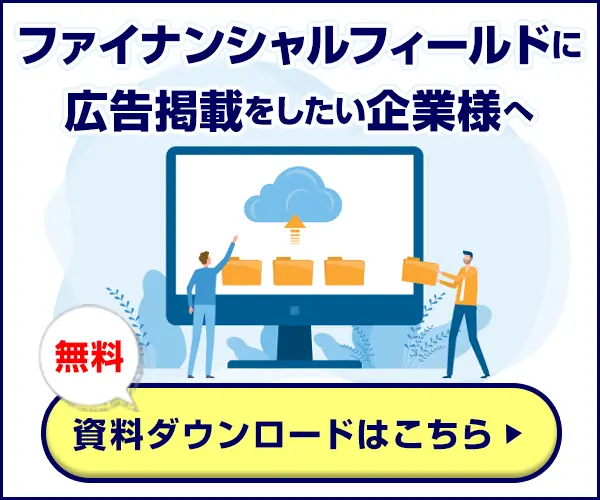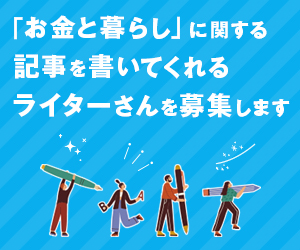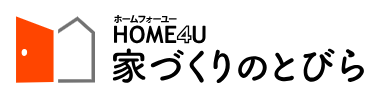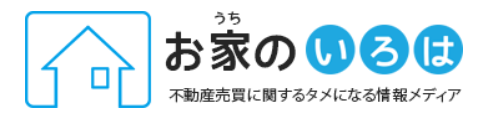2000万円不足するという根拠は、2017年の総務省の「家計調査報告」によるものです。前述の世帯では毎月5.5万円不足が生じ、30年間ではおよそ2000万円になるという計算になります。
しかし、現在の調査では不足額が異なることをご存じでしょうか?
今回は、2021年に行われた総務省の「家計調査報告」を基に、老後の収支がどのようになっているかを一緒にみてみましょう。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
不足額は減っている
総務省による2021年の「家計調査報告」より、「65歳以上の夫婦のみの無職世帯」の家計収支の結果は以下のとおりです。
可処分所得が20万5911円、消費支出が22万4436となっており、これらを計算すると不足分は1万8525円となっています。
これを30年とした場合、およそ667万円の不足となり、2019年の老後2000万円問題発表時と大きくかけ離れています。
どうして不足額が減ったの?
なぜ不足額が減ったのでしょうか? それは、その年ごとの「平均値」を基に収支を計算しているためといえます。
特に2019年の老後2000万円問題発表時に用いられたデータは、「夫65歳、妻60歳」でしたが、2020年からは「共に65歳以上」に変更されています。年金の支給開始が65歳ですから、結果に違いが出てしまいます。
このように、データの対象に変更があったり、収支をあくまで平均から求めていたりするため、毎年結果が異なるといわれています。
家計管理や 資産形成の重要性は変わらない!自分の数字に目を向けよう
不足額が減り、不安が小さくなったかもしれません。しかし、過剰な心配も油断もしない方が賢明といえるでしょう。
なぜなら、あくまでデータは平均値だからです。各世帯での可処分所得と消費支出、いずれも平均値どおりの数字には、ならないことでしょう。
最も大事なことは、ご自身の家庭の収支に目を向けることです。もっと不足額が多い世帯もあるはずですし、逆に年金で生活費がすべて賄える家庭もあるかもしれません。
これらのことから、家計を管理することは非常に重要です。収支バランスを意識した生活ができるよう、家計管理を日々こころがけましょう。
資産形成の重要性も変わりません。NISAやiDeCoといった税制が優遇されている制度は、有効活用してください。
日本人の平均寿命は延びており、その分、お金は多くかかります。これらの制度を利用している人は、変わらず運用を続けましょう。
資産形成に取り組んでいない方は、早めに取り組んでみるとよいでしょう。長期積み立て投資により、資産を大きくできます。
まとめ
家計調査報告を基に、老後の家計収支をみてみました。
2019年の老後2000万円問題が世間をにぎわせたときとは、不足額が異なっています。しかしだからといって、安心してはいけません。
今や人生100年時代といわれており、長いスパンでの資産形成や、家計の見直しは今後も変わらず重要だからです。
出典
総務省 家計調査報告 家計収支編 2021年(令和3年)平均結果の概要
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部