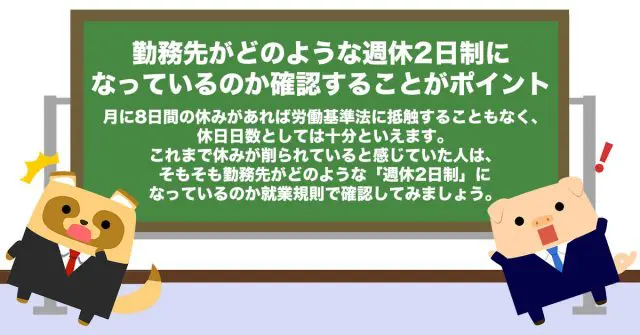【ブラック化の前兆?】「週休2日制」から「月8日休日」へのメリット・デメリットとは?

今回は、会社の休日について正しく判断するために「週休2日制」の基本的な考え方や「月8日休日」になるメリット・デメリットについて解説していきます。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
「週休2日制」は必ずしも毎週2日休める制度ではない
「週休2日制」と聞くと、毎週2日の休日があると考える人は多いのではないでしょうか。ところが、そうではありません。毎週必ず2日の休日があるのは「完全週休2日制」の場合です。
「完全週休2日制」と「何らかの週休2日制」では意味がやや異なります。厚生労働省が調査した「令和3年就労条件総合調査の概況」で、主な週休制の形態別企業割合を見ていくと「何らかの週休2日制」を採用している企業は83.5%です。
そのうち「完全週休2日制」を採用している企業は48.4%にとどまり、残り35.0%は「完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度」で、週休2日制といっても隔週にしているなど、毎週必ず2日の休みがあるわけではありません。「週休2日制」としていながら休みが少ないと感じたら、自分の会社の休日がどのようになっているか「就業規則」で確認しておく必要があります。
「週休2日制」から「月8日休日」へ変更になるメリット・デメリット
「月8日休日」としている場合は、月ごとの労働日数に関係なく毎月8日間の休日が与えられるということです。では「週休2日制」から「月8日休日」へ変更になる場合、実際にはどのようなメリットとデメリットがあるのか見ていきましょう。
・「月8日休日」になるメリット
これまで「何らかの週休2日制」だった会社は、月8日以上休めていない可能性が高いといえます。例えば、隔週で週休2日にしている場合は6~7日程度が毎月の休日数になります。「月8日休日」に変更になれば毎月8日間は必ず休めるため、休日数が増える点がメリットです。毎月の休みが必ず8日間取れるということで、年間を通してプライベートの予定が組みやすくなるかもしれません。
また、実際には「何らかの週休2日制」だったのに「完全週休2日制」だと誤解していた人もいるでしょう。その場合、毎月8日間休めるようになるので満足度が上がるというメリットもあります。
・「月8日休日」になるデメリット
「完全週休2日制」を導入していた会社なら、年間の休日数が減ることがデメリットです。「完全週休2日制」であれば、月によっては5週ある月は10日間休日が取れます。ところが「月8日休日」になれば、本来10日間休日がある月でも8日間しか休めなくなります。
しかし、1週間に1日の休日もしくは4週間を通じて4日以上の休日が取れていれば労働基準法に触れることはありません。違法性はないものの、働く側としては労働条件が悪くなったと感じるでしょう。
勤務先がどのような週休2日制になっているのか確認することがポイント
「週休2日制」から「月8日休日」になるというだけでは、一概にブラック化とみなすことはできません。そもそも、月に8日間の休みがあれば労働基準法に抵触することもなく、休日日数としては十分ともいえます。
これまで休みが削られていると感じていた人は、そもそも勤務先がどのような「週休2日制」になっているのか「就業規則」でしっかり確認してみることです。その上で、メリットとデメリットを考えてみましょう。
出典
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 令和3年就労条件総合調査の概況
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部