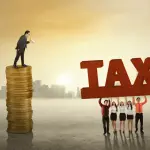親が認知症になったら預金が出せないというのは分かりました。でも本人が施設に入る費用なら大丈夫ですよね?

そこで本記事では、認知症で銀行口座が凍結した場合、家族は施設の費用をおろせるのかについて、全国銀行協会が出した指針の内容をもとに解説します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも
【PR】イエウール
目的が施設費用や介護費用でも、本人が認知症だと原則としてお金は引き出せない
銀行などの金融機関は、原則として口座の名義人本人とのみ取り引きを行います。本人が高齢になり認知症などで判断能力が低下した場合、金融機関はお金の引き出しなどの取り引きを制限します。これが、いわゆる口座凍結です。
金融機関口座の凍結は本人の財産保護を目的としています。たとえ本人の介護費や施設の入居費が目的であっても、本人の意思が確認できなければ、銀行は家族や親族にお金を下ろさせてくれません。
基本は成年後見制度で対応する必要がある
口座名義人の認知症発症によって、預金の払い出しや口座の解約などに支障が出るケースが増加していることを受け、全国銀行協会は2021年に、認知症患者の家族が預金引き出しを求めた場合の金融機関の対応指針を発表しました。この指針の中では、認知症患者との取り引きの一般的な対応として「親族などに成年後見制度等の利用をうながす」ことが示されています。
そのため、家族が認知症を発症して金融機関の取り引きなどに支障が生じそうな場合は、早めに成年後見制度の利用を検討する必要があるでしょう。すでに認知症で判断能力が低下している場合、利用できるのは法定後見制度のみです。
また、親族などが任意代理人となって取り引きする方法もありますが、本人の意思のもと法的に認められる代理権の付与が行われており、銀行に届け出ている必要があります。認知症発症後に手続きするのは難しいでしょう。
【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!
【PR】イエウール
応急的に家族や親族の代理が認められるケースも
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人等の選任手続きをする必要があります。申し立てから成年後見が開始するまでに2ヶ月程度かかるケースもあり、お金がすぐに必要なときに対応できません。
そのため、全国銀行協会の指針では、本人の判断能力が低下し、成年後見制度の利用もしていない場合には、家族や親族による取り引きを限定的に認める考えも示されています。ただし、すべての取り引きに応じるのではなく、医療費や介護費、生活費など本人の利益にとって必要な費用に限り対応するといった内容です。
また、全国銀行協会の指針は全金融機関に対応を指示するものではないため、実際の運用は金融機関ごとに異なることに注意する必要があります。
認知症で判断能力が失われる前に親の財産管理の対策を
親の介護費用や施設の入居費用が必要なときに困らないために、本人が元気なうちにスムーズに財産管理ができる対策をしておくことが重要です。主な手段としては、任意後見制度や家族信託などが挙げられます。
■任意後見制度
本人の判断能力があるときに契約で任意後見人(受任者)や任せたい財産管理の範囲を契約で定めておき、本人の判断能力が低下したあとに家庭裁判所に申し立てて契約を発効させる制度。
■家族信託
本人(委託者)の財産を信託財産として家族(受託者)に託し、信託契約に定めた目的に沿って管理や運用を任せる制度。
また、いざというときに財産の状況や介護方針に関する希望が分からず戸惑わないよう、普段からお金や介護に関する情報を親と共有しておくことも大切です。
本人の生活に不可欠なお金でも口座が凍結すると簡単には引き出せない
親の認知症で銀行口座が凍結されると、家族や親族でもお金を引き出せなくなります。目的が施設の費用や医療費などの支払いでも、原則として同じ対応です。
親の認知症により口座凍結に陥ったら、成年後見人などの法定代理人を立てる必要があります。また、全国銀行協会の指針により、応急的に家族や親族でも取り引きができるケースもありますが、限定的な対応でしかありません。
親の認知症発症で施設や介護の費用が捻出できなくなる前に、親が元気なうちに家族で対策を講じておきましょう。
出典
法務省 成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A Q3~Q15 「法定後見制度について」
法務省 成年後見制度・成年後見登記制度 Q16~Q20 「任意後見制度について」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー