コロナ禍による収入減で年金保険料が免除になった40代。将来の年金額、いくら減る?
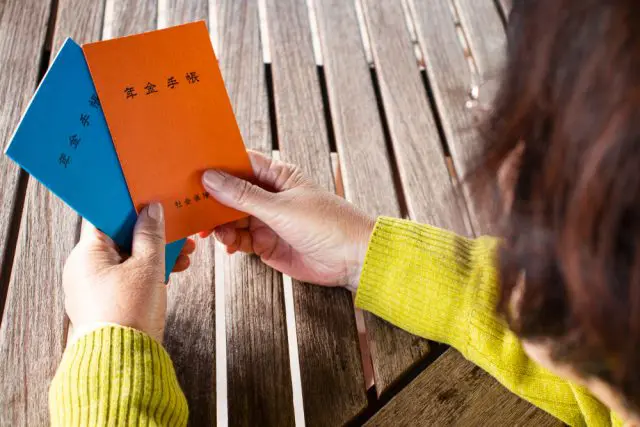
一方で、将来受け取れる国民年金の額が減ってしまうこともあるため、事前に制度の概要やどの程度年金額が減るのかについて把握しておくのが重要です。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
国民年金保険料納付に関する臨時特例とは?
臨時特例に基づいて、新型コロナウイルスの影響で、国民年金保険料の納付が困難になった方向けの保険料免除の申請手続きが、令和2年5月1日から開始されました。
日本年金機構によると、以下の条件をどちらも満たした場合に申請が可能となっています。
●令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
●令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
申請にあたっては、原則として所得を証明する書類の提出が必要ありません。年間の収入を正確に計算するわけではなく、令和2年2月以降の収入が減少した任意の月の収入に基づいて見込みの年収を申告します。
申告した所得(手取り収入から必要経費を引いて残った額)が以下で示した金額以下の場合に、年金保険料の全額または一部が免除される仕組みです。
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
例えば、40歳で扶養親族が妻と子の2人のケースでは、計算式が(2+1)×35万円+32万円となり、137万円以下の所得であれば、全額免除となります。
国民年金の保険料は毎年見直しとなっており、令和3年度は年間で「約20万円」と家計の負担は少なくありません。新型コロナウイルスの影響で、保険料の支払いが難しい場合は申請を検討した方がよいでしょう。
保険料を支払わないままにしてしまうと未納扱いとなり、年金の受給額が減ってしまったり、年金自体が受け取れない可能性もあります。万が一、未納期間中に亡くなったり、病気やけがで障害状態となってしまうと、遺族年金や障害年金が受け取れないリスクもあるため、注意が必要です。
コロナ禍の特例で年金保険料が全額免除になった40代は、将来の年金額が約2万円減る
年金保険料の免除が適用された場合には、保険料を全額納付した場合と比べて将来受け取れる年金額が減少します。
日本年金機構によると、特例が適用された期間について、実際に受け取れる年金額は以下のように決まっています。
| 全額免除 | 保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1 |
| 4分の3免除 | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5 |
| 半額免除 | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6 |
| 4分の1免除 | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7 |
具体的にいくら年金額が減るのか、下記のケースで計算してみましょう。
●現在40代
●20歳から60歳までの40年間、年金保険料を納付した場合に受け取れる年金額は年額78万900円
●臨時特例により令和元年度から3年度まで、日本年金機構によると最大29ヶ月間免除が適用される
全額免除の場合
78万900円×29/480×1/2=2万3589円
4分の3免除の場合
78万900円×29/480×3/8=1万7692円
半額免除の場合
78万900円×29/480×2/8=1万1794円
4分の1免除の場合
78万900円×29/480×1/8=5897円
毎年受け取る年金額は、上記で示した分だけ減少します。
追納制度を活用して支給される年金額を増やそう
年金は老後の貴重な収入源です。毎年2万円程度であっても、長期間にわたって受給するケースがほとんどのため、受け取れる額は少しでも多い方がよいでしょう。
日本年金機構によると、免除の特例が適用された期間の保険料には、10年以内であればさかのぼって保険料の納付ができる追納の制度があります。
ただし、免除を受けてから3年目以降は、納付する保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。新型コロナウイルスの影響が落ち着き、収入が安定してきたタイミングで、なるべく早めに保険料を支払うのがおすすめです。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
出典サイト 日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
出典サイト 日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

































