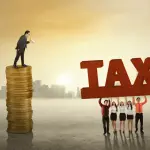新社会人、初任給が高いので一定額を貯蓄したいです。財形貯蓄以外にNISAやiDeCoもやるべきですか?

少額からコツコツ積立ができ、コストが安く、税優遇のある新NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)による積立投資がお勧めです。

ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/
NISAとは
新NISAは日本国内に住んでいる18歳以上が利用できます。通常、株式や投資信託の売却益などには約20%の税金がかかりますが、新NISAで株式や投資信託を購入すると、配当金や値上がり益などの運用益に税金がかかりません。
口座開設期間(制度の期限、買付可能期間)は恒久、非課税保有期間は無期限です。これにより、投資期間を心配することなく、より長期的な視点にたって資産運用ができます。
新NISAにはつみたて投資枠と成長投資枠があります。つみたて投資枠で積立投資を続けながら、成長投資枠で個別銘柄に一括投資することも可能です。
つみたて投資枠では、長期の積立・分散投資に適していると金融庁が指定した投資信託を、成長投資枠では上場株式・投資信託を購入できます。ただし、年間投資額には上限があります。つみたて投資枠は120万円、成長投資枠240万円で生涯を通じての非課税保有限度額は1800万円(うち成長枠は1200万円)です。
なお、投資対象を売却した場合、翌年以降に売却した商品の取得金額(簿価)の分だけ非課税となる投資枠が復活、そして再利用が可能になります。
新NISA制度で投資を始めるには、証券会社や銀行などの金融機関でNISA口座を開設する必要があります。口座は1人につき1口座のみ開設可能です。金融機関の変更については、年単位で可能です。
金融機関によって手数料や取り扱い金融商品が異なります。どんな金融商品に投資したいのかよく検討したうえで口座を開設する前に決めておくといいでしょう。
初心者の方は「特定口座・源泉徴収あり」がお勧めです。特定口座にすると、投資商品の1年間の損益を金融機関が計算してくれ、年間取引報告書という書類にまとめてくれます。
さらに、源泉徴収口座を選ぶと、投資商品の損益が発生する都度、金融機関が損益計算を行い、所得税・住民税が源泉徴収され、源泉徴収された年間の税金は、金融機関が代わりに納付するので、確定申告をする必要がなく手続きが簡単です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは
iDeCoは自分で拠出額を決め、自ら金融商品を運用し、その運用実績により将来の資産の受取額が決まる私的年金制度です。基本的に20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者の方が加入できます(自営業者や専業主婦(主夫)は60歳未満)。
投資対象は、保険や定期預金などの元本確保型商品とリスク商品の投資信託があります。
iDeCoは、運用している期間だけではなく、掛金拠出時・資産の受取時にも税制優遇があります。すなわち、掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除できます。
仮に毎月の掛金が2.3万円の場合、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間5.52万円、税金が軽減されます。60歳以降、形成した資産を受け取るとき一時金で受け取れば「退職所得控除」の対象、年金で受け取れば「公的年金等控除」の対象となります。
掛金は毎月5000円以上1000円単位で、職業等ごとの限度額の範囲内で自由に設定できます。
拠出金額の月額上限は、自営業者など6.8万円、専業主婦(夫)2.3万円、会社員(企業年金等未加入)2.3万円、会社員等(企業型DC、企業型DCとDB等、企業型DB等に加入)2.0万円です。
iDeCoを始めるには金融機関で専用の口座を作る必要があります。金融機関によって取り扱う運用商品やサービス内容、毎月の管理手数料、投資信託の信託報酬など運用商品にかかる手数料、給付時の手数料等が異なります。口座は1人につき1つしか持てません。
iDeCoに加入する場合は、これらを確認のうえ、手数料の安い金融機関を1社選びましょう。
まとめ
iDeCoとNISAの特徴をよく理解し目的に応じてうまく使い分けましょう。
例えば、老後の資産形成は原則60歳まで換金できないiDeCo、教育資金など中期的な資金ニーズにはNISAを活用するなど。20代であれば60歳まで30年以上運用できるのでiDeCoでは株式型の投資信託で運用するとよいでしょう。一時的に損失が出ても、その後の運用期間で損失を取り戻せる可能性があるからです。
出典
金融庁 NISAを知る
国民年金基金連合会 iDeCo 公式サイト
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。