最近よく聞く「静かな退職」だけど、2025年は「リベンジ退職」がトレンドに!? なぜ起きているの? 理由を解説
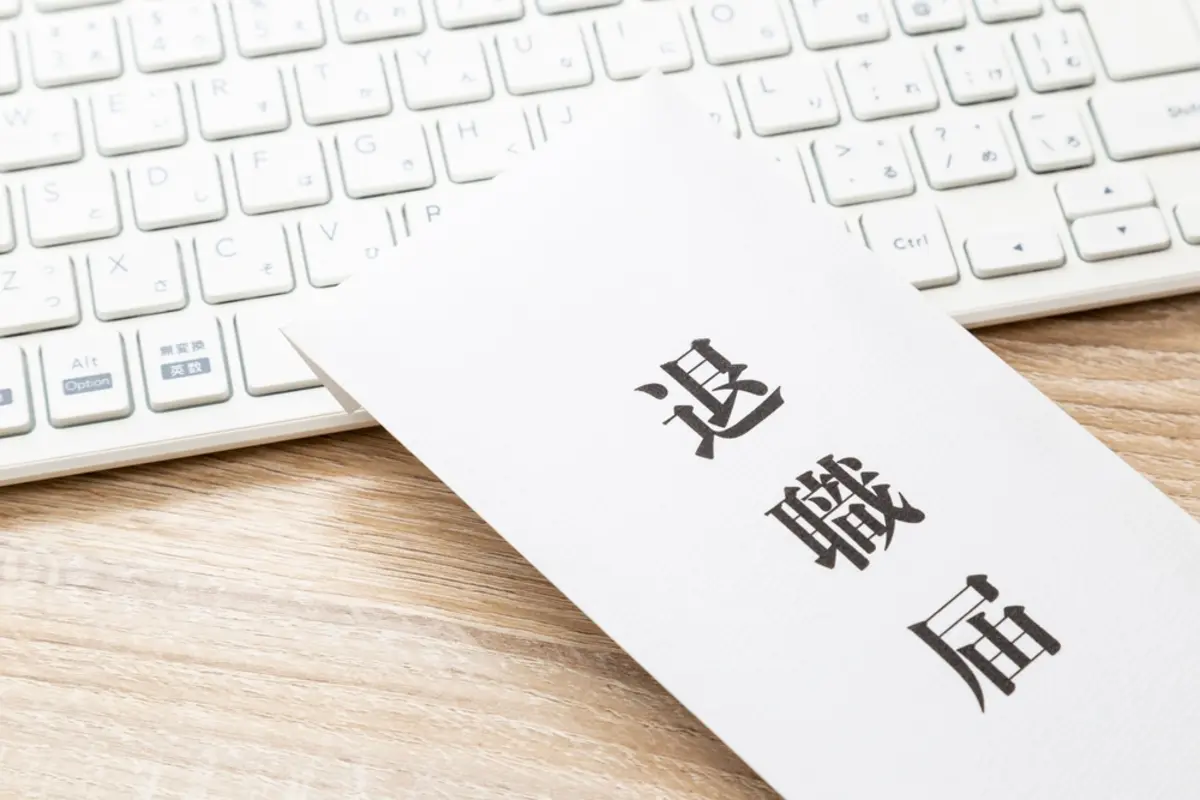

FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント
世界では50%以上が「静かな退職(Quiet Quitting)」状態!?
「静かな退職」とは、企業に勤める労働者が必要最低限の仕事しかせず、それ以上のことを積極的には行わない状態でありながら、自発的な退職・転職は望まないことを言います。アメリカで2022年の夏ごろ、「TikTok」で公開された動画をきっかけにこの言葉が広がっていったとされています。
アメリカの調査会社であるギャラップ社が、2022年から2023年に世界中(160カ国、12万2416人が対象)で行った調査「2023 State of the Global Workplace」によると、仕事への関与の仕方について「打ち込んでいる」「打ち込んでいない」「積極的に関与していない」の3つのカテゴリーに分け、「打ち込んでいない」=「静かな退職」をしていると分類された人は全体の59%にのぼると結論づけました。
また、同じ調査では回答者の44%が「前日の仕事の影響で、一日の大半でストレスを感じている」とも回答しており、労働者が自分の業務から多大なストレスを受けており、仕事に対するモチベーションが落ちていることが読み取れます。
キャリアコンサルタントである筆者の視点から見て、この傾向は日本国内でもかなり強まっているように感じられます。特に、10~20代の若い就業者の人や新卒就活生でも、仕事に対するモチベーションが低く、「できる限り早く『FIRE』して、仕事をせずに生きていきたい」と真剣に考えている複数の人と面談したことがあり、個人的には衝撃でした。
正社員でありながら、「上司に言われたことだけやる」というスタンスでは、自身の成長や出世はもちろん、昇給を望むことも難しく、「FIRE」に必要な資産を蓄えることもできないでしょう。それはかえって自分の希望からは遠ざかる結果となるのではないかと思いましたが、よく話を聞いてみると「静かな退職」の状態で満足していると本人は考えているようでした。
「リベンジ退職」はなぜ起きるのか
一方、最近急激にトレンドになっているとされる「リベンジ退職」は、「静かな退職」に比べると攻撃的で、「職場に対する不満が引き金となり反発する意思を示すなど、報復心を持って辞める行為」とされます。「静かな退職」と比べると、会社に在籍しつづける意志がない点が最も異なると言えるでしょう。
会社に強い不満を持って退職した人は、なかば意図的に在籍していた会社の内部データ、技術、経営戦略などを転職先に持ち出していきかねません。さらに、SNSなどで前職の企業・上司本人に対する誹謗(ひぼう)中傷を行うこともありうると考えると、より会社側にとってダメージが大きいと思われます。
「静かな退職」も「リベンジ退職」も、労働者が勤務している会社に強い不満を持つことが発生する1番の原因ですが、これらの現象がある種のブームになった背景には、「深刻な人手不足」があると筆者は考えています。
会社としては「今の従業員に辞められたら困る」という状態なので、従業員側はそれを逆手に取って、「静かな退職」をする人は必要最低限の業務しかしないことで、「リベンジ退職」では会社に直接的なダメージを加えることで、それぞれ勤務している会社に不満を表明し、うっぷんを晴らすことが可能な環境ができてしまっています。
特に近年のアメリカにおいてはコロナ禍が落ち着いて労働市場が回復し、労働者にとって転職しやすい環境がおとずれたことが「リベンジ退職」を後押ししている一面もあるでしょう。
会社側としては、従業員の「リベンジ退職」はもちろんのこと「静かな退職」も、放置すれば組織全体のパフォーマンス低下につながるため、可能な限り従業員が不満を抱え込まないようにしていかなくてはいけません。普段から従業員とのコミュニケーションを密にするほか、給与面などでの待遇改善も絶えることなく行っていく必要があると言えます。
まとめ
「静かな退職」も「リベンジ退職」も、従業員側が会社に強い不満を持つことが原因で発生します。これらの現象が一種のブームになっているのは、世界的に深刻な人手不足が起きており、「今の従業員に辞められたら困る」という会社の状況を従業員側が敏感に読み取り、逆手に取っているからではないでしょうか。
企業側としてはこれらの現象を深刻に受け止め、従業員側が不満を溜め込まないようなコミュニケーションを取っていくこと、待遇の改善を進めていくことが求められています。
執筆者:山田圭佑
FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント

































