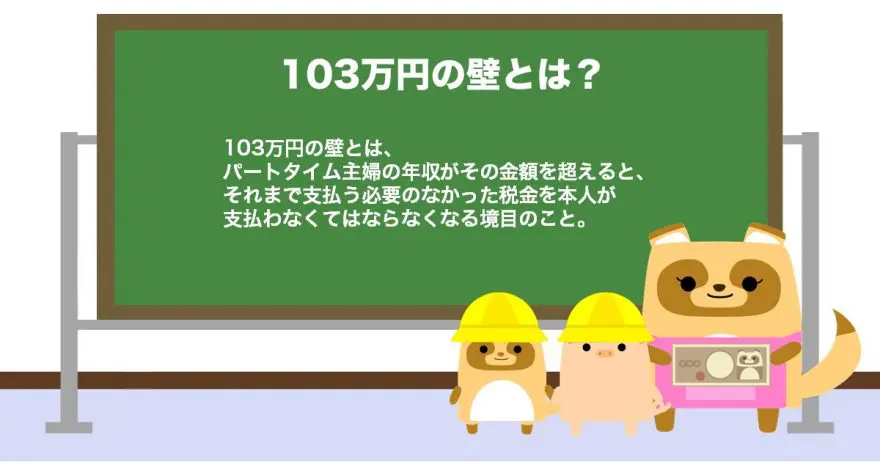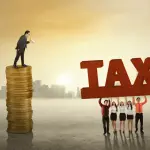専業主婦がパートタイムで働くときのさまざまな壁<その4>~税金の壁 103万円の壁

「その4」からは税金の壁として、103万円・150万円の壁の内容について説明していきます。

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。
現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。
ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。
FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。
2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。
現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。
早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。
サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow
税金の壁の意味
パートタイムで働く専業主婦の年収が税金の壁、例えば、103万円の壁を超えた場合、本人の収入から所得税、住民税などの税金を支払わなければなりません。その分、手取り収入が減少することになります。
税金の壁の意味はそれだけではなく、パートタイム主婦の扶養者となっている夫が税金の計算上、配偶者控除などの控除を受けられなくなり、その分の税負担が増加して夫の手取り収入も減少します。
すなわち税金の壁は、パートタイム主婦の手取りの減少と夫の手取りの減少について、両方の観点から見ていかなければなりません。これがまず初めに注意すべき点です。
103万円の壁とは?
103万円の壁とは、パートタイム主婦の年収がその金額を超えると、それまで支払いの必要がなかった税金について、本人が支払わなくてはならなくなる境目のことをいいます。103万円の壁を所得税の計算上から見ると、次のようになります。
年収:103万円
給与所得控除(※1):△55万円
合計所得金額:48万円
基礎控除(※2):△48万円
課税所得金額:ゼロ
所得税は、収入から国が認めた必要経費や控除額(税金がかからない金額)を差し引いて課税所得金額を算出し、課税所得金額に対して税額の計算を行います。パートタイム主婦に対して認められる控除は次のとおりです。
(※1)給与所得控除
給与所得者に対して認められる控除。年収103万円の場合は55万円
(※2)基礎控除
合計所得2500万円以下の人に認められる控除。年収103万円の場合は48万円
すなわち、パートの年収が103万円以下であれば、控除額を差し引いた課税所得金額がゼロになるため、所得税はかかりません。一方、年収103万円を少しでも超えると、超えた部分に対して税金がかかることになります。
ここまでの説明は所得税(復興特別所得税については少額なので説明を省略)に関するものですが、個人の所得に対してかかるもう一つの税金、個人住民税(以下「住民税」)の場合は計算が少し異なります。
年収:100万円
給与所得控除(※1):△55万円
合計所得金額:45万円
住民税の場合、合計所得金額が45万円以下であれば非課税となります。合計所得金額が45万円を超えた場合、基礎控除を引いて課税所得金額を計算します。
年収:101万円
給与所得控除(※1):△55万円
合計所得金額:46万円 → 住民税課税
基礎控除(住民税の場合)(※3):△43万円
課税所得金額:3万円
所得税と異なり、基礎控除の金額が43万円(※3)なので、年収100万円を超えるとパートタイム主婦に対して住民税がかかることになります。それほど大きな違いではありませんが、違いがあることは覚えておく必要があります。
「103万円の壁」を正確にいうと、「103万円または100万円の壁」となることが分かります。
図表1
パートタイム主婦の年収が本人の税額に与える影響 (単位:万円)
| パートタイム主婦の年収 | 100万円 | 103万円 | 105万6000円 | 130万円 | 150万円 | 175万円 | 201万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人の所得税 (復興特別所得税を除く) |
0 | 0 | 1000円 | 1万4000円 | 2万4000円 | 3万6000円 | 4万9000円 |
| 本人の住民税(均等割・調整控除を除く) | 0 | 5000円 | 8000円 | 3万2000円 | 5万2000円 | 7万7000円 | 10万3000円 |
| 本人の税金計 | 0 | 5000円 | 9000円 | 4万6000円 | 7万6000円 | 11万3000円 | 15万2000円 |
※筆者作成
まとめ
「その4」では、パートタイム主婦の年収が、その金額を超えると本人が税金を支払わなければならなくなる「103万円の壁」、または「100万円の壁」(通常の場合は両方を合わせて「103万円の壁」といいます)について説明しました。「その5」では、「150万円の壁」を説明したいと思います。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー