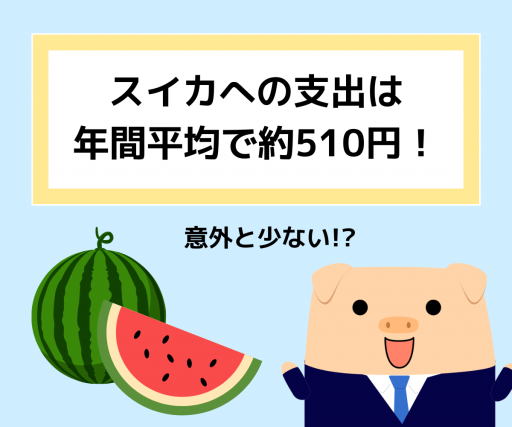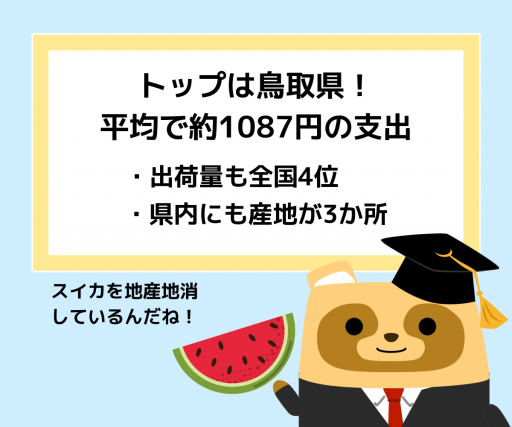【あなたはスイカ県民?】一番「スイカ」を食べている県はどこ?

1970年代半ばをピークに国産果実の消費量は減少傾向にありますが、夏の風物詩スイカも例外ではありません。そんな時代にあって、最もスイカを食べている県はどこなのか?本記事では、スイカの基礎知識や1人当たり支出金額と消費量が最も多い県を紹介します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
スイカは果物か野菜か?
スイカは野菜でもあり果物でもあります。本項目では、知っているようで知らないスイカの基礎知識を紹介します。
・スイカの歴史
アフリカ原産のスイカが中国を経由して日本に入ってきたのは、16~17世紀の頃とされています。現在のスイカは、明治~大正時代にかけて、米国、ロシア、中国などからもたらされた苗が自然交雑を繰り返す中で生まれた、「大和」という品種が元になっています。
・果物か野菜か? 農林水産省と厚生労働省で異なる分類
スイカは、「果実的野菜」です。果実的野菜とは、「園芸学的には野菜に分類される、果物のように甘い植物」のことです。スイカの他には、イチゴやメロンが該当します。園芸学では、栽培に2年以上必要で食べられる果実のなる木を「果樹」と呼んでいますが、果実的野菜は一年生草本植物です。そのため、園芸学の観点からスイカは野菜に分類されています。
なお、栽培植物を所管する農林水産省では、スイカを野菜に分類した上で果実的野菜として扱っています。ただし、国民の栄養調査などを行う厚生労働省の分類では果物です。このようなことから、一般的な認識として、スイカを果物として扱うことに問題はありません。
・スイカは水でできている?
スイカは、全体の約90%が水分です。その他にも、糖分とカリウムなどのミネラルや各種ビタミン類などを含有しています。また、特徴的な果肉の赤色は、カロテンの1種であるリコピンによるものです。多量の水分と適度な糖分を含むため、塩をふりかければ熱中症の予防効果が期待できます。
最も消費量が多いのは鳥取県
総務省統計局の「家計調査」と「小売物価統計調査」などを利用して物価を反映させた上で、スイカの消費量が最も多い県を算定しました。その結果、令和元年に全国で最もスイカを消費したのは鳥取県(鳥取市)で、1人当たり0.56個でした。金額ベースでは年間1087円をスイカに費やしています。
各都道府県がスイカに支出した1人当たりの平均は510円程度です。鳥取県では、その約2倍の金額をスイカに費やしていることになります。
総務省の小売物価統計調査によると、消費者物価地域差指数の全国平均を100とした場合における鳥取県の食料指数は101.7で、平均を若干上回っています。このことから、食品物価の高さが影響した可能性が考えられます。
ただ、鳥取県にはスイカの産地が県内に3カ所あり生産量も比較的多く、令和元年の出荷量は1万6400トンで全国4位でした。そのため、県内でも比較的多くのスイカが消費されていて、1人当たりの支出額も全国平均を大きく上回っている可能性があります。
つまり、令和元年に鳥取県がスイカ消費量日本一になったのは、食品物価の高さと生産量の多さが影響した結果であるのかもしれません。
夏の風物詩の一つとして残したい果物
スイカは、その味や歯ざわりを楽しむだけでなく熱中症予防にも効果的な果物です。最近はカットされたスイカも販売されているため、1人暮らしの人も手軽に購入できます。複数のサイズ、種なし、黄色い果肉といったさまざまな種類があるのもスイカの魅力です。これからも、夏の風物詩として愛され続けてほしい果物の一つです。
出典
農林水産省 7 果実の消費動向 ①(消費動向の推移)
農林中金総合研究所 果実の消費と生産の状況
農林水産省 野菜類の区分はどのようになっているのか教えてください。
農林水産省 果樹とは
スイカ倶楽部 スイカの成分と効能
総務省統計局 家計調査
総務省統計局 小売物価統計調査
農畜産業振興機構 すいかの需給動向
総務省 小売物価統計調査(構造編) -2019年(令和元年)結果-
北陸農政局 すいかの種類
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部