親族に「生活保護受給者」のいる大学生です。就職したら親族を養わなければなりませんか?
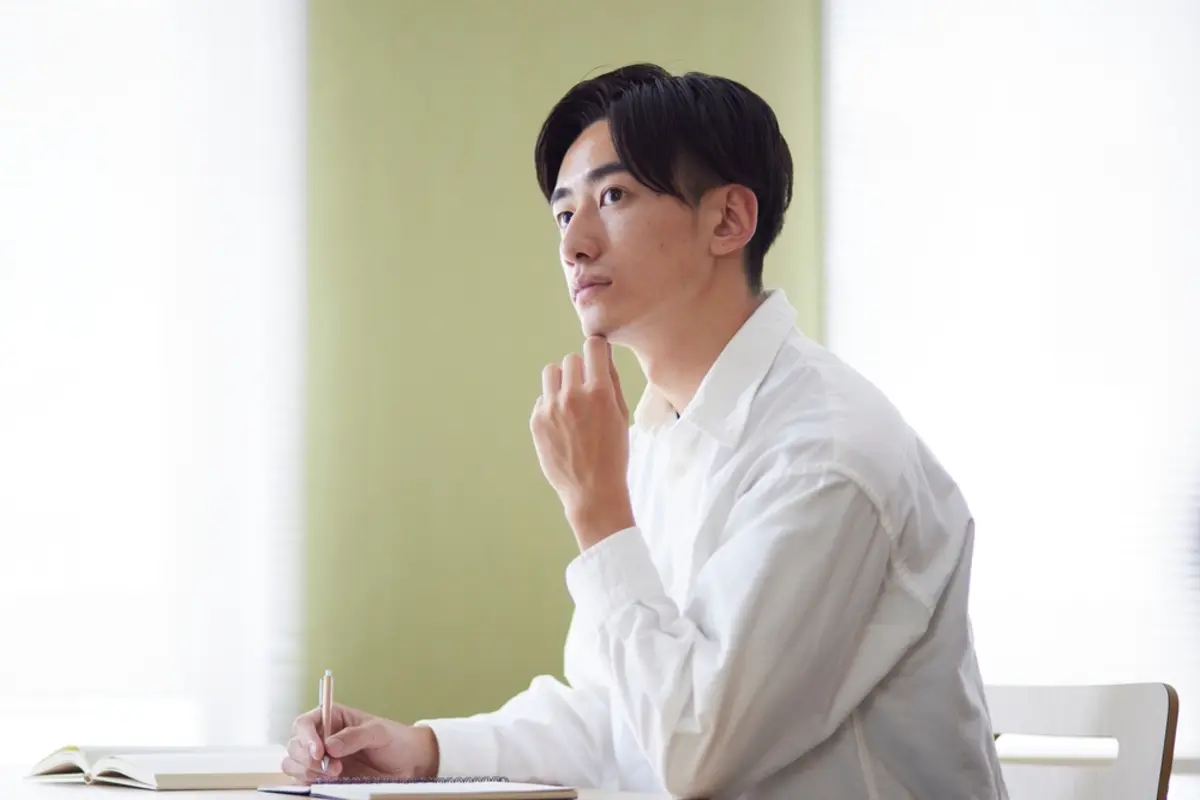
この記事では、生活保護と扶養義務の関係や、親族に生活保護受給者がいる場合、就職後どのような影響があるのかについて解説します。

行政書士
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
生活保護と扶養義務
日本では、親や子ども、兄弟姉妹といった親族に対しての扶養義務があります。これは民法で定められており、親族が経済的に困窮している場合、可能な範囲でその生活を支える義務があるというものです。ただし、あくまでも「可能な範囲」というのがポイントで、自己の生活に優先すべきというものではありません。
一方で、生活保護は国が最低限度の生活を保障する制度です。親族による扶養は生活保護より優先されると定められていますが、先に述べたように、扶養義務がある親族全員が必ず経済的支援をしなければならないわけではありません。支援が可能かどうかは、それぞれの収入や生活状況によって判断されます。
就職後に扶養義務を果たす必要があるか
就職して安定した収入を得られるようになると、理論上は親族を扶養できると判断される可能性があります。しかし、実際にそう判断されることはほとんどないと考えてよいでしょう。
大学卒業後に就職すると、初年度の年収は300万円程度から350万円程度と想定されます。その他の資産状況にもよりますが、これは「親族を容易に扶養できるほど余裕がある」とは言い切れない年収です。
仮に、その後400万円、500万円、600万円と年収が増えていったとしても、扶養義務が課されることはほとんどないと考えられます。先に述べたとおり、扶養義務よりも自身の生活が優先されるためです。
また、親族関係が疎遠である場合や、過去に争いが起こったなど深刻な事情がある場合は、扶養を拒否することも可能です。
なお、自分が扶養しなかったため親族が生活保護を受けることになったとしても、何か罰則があるわけではありません。金銭的な支援を強く求められたとしても、負担を強制されることは基本的にありません。
どうしても不安があるときは?
生活保護受給者の扶養義務に関して不安があるときは、福祉事務所に相談することが大切です。自分の収入や生活状況を伝えれば、具体的な扶養義務の範囲や支援方法について説明を受けることができます。
仮に扶養することになったとしても、自分の生活が苦しくなるほどの支援を求められることはありません。特に、就職したばかりで経済的に安定していない場合は、自分の生活を最優先に考えた範囲での支援で問題ないと判断されることが多いでしょう。
また、被扶養者への支援は、金銭の負担を伴うものに限定されているわけではありません。日常生活で必要な物資の提供や、相談相手になることなど、無理のない形で支援を行うことも選択肢の一つです。
まとめ
親族を養わなければならないかどうかは、個々の収入や生活状況に大きく依存します。大学卒業後安定した収入を得たとしても、年収300万円から400万円程度であれば、扶養義務が課されることはまずないと考えられます。
親族に生活保護受給者がいても、自分の生活を最優先に考え、無理のない範囲で対応することが基本です。法的な拘束力は弱いため、必要以上に負担を感じる必要はありません。
とはいえ、実際の親族との関係や生活状況によっても判断は異なるため、福祉事務所や専門家に相談し、適切な対応を考えることも大切です。
自分の生活を安定させることが、長期的には周囲を支える力にもつながります。身内に生活保護受給者がいるからと焦らず、自分の将来設計をしっかりと立てていきましょう。
執筆者:柘植輝
行政書士

































