子どもを大学に通わせるには、親の年収はどのぐらいあったほうがよい? 奨学金を使う場合と使わない場合に分けて目安を解説
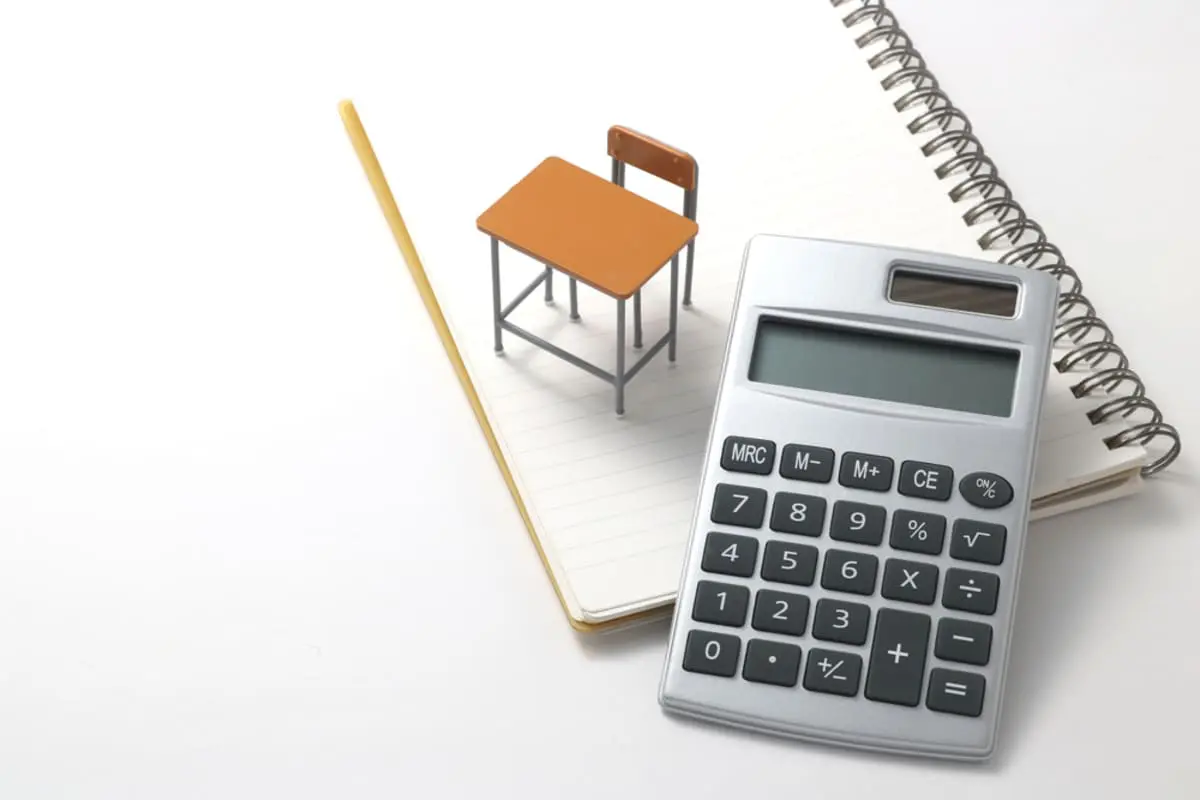
本記事では、大学進学のための収入の目安を、奨学金を利用する場合と利用しない場合に分けて解説します。また、大学無償化制度の概要や利用方法についても触れますのでぜひ参考にしてください。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
大学進学にかかる費用の概要
子どもが大学に進学する際、家庭の収入状況によっては、進学費用が大きな負担になる場合があります。大学の進学費用は、主に学費、入学金、教材費、生活費(寮費や家賃)などに分かれます。私立大学や都市部にある大学の学費は高額であり、年間100万円以上かかることが一般的です。
一方、国公立大学の場合は、私立に比べて学費が低いものの、依然として年間数十万円から100万円程度の費用が必要です。いずれにせよ、大学進学は家計に大きな影響を与えることが分かります。奨学金や大学無償化制度を利用することで負担を軽減できる可能性もありますが、事前の計画と制度の理解が重要です。
奨学金を利用した場合の収入の目安
奨学金を活用することで、大学進学の費用を軽減することが可能です。
例えば、日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金の支援が受けられます。支援によって学費や生活費を賄うことはできますが、卒業後の返済義務が生じるため、子どもの将来に与える影響を考慮する必要があります。
仮に、奨学金を利用して大学費用の一部を賄う場合でも、世帯年収が400万円から600万円程度あれば、ある程度余裕を持って進学費用を負担できるといわれています。ただし、家計状況や地域差による生活費の変動を考慮することが重要です。
奨学金を利用しない場合の収入の目安
奨学金を利用しない場合、大学進学費用はすべて自己負担となります。この場合、家庭の年収が800万円以上であれば、私立大学や都市部での進学費用を比較的安定して支払えるといわれています。
ただし、複数の子どもが大学進学を希望する場合や、不測の事態に備えるための貯蓄は必要である点も考慮しなければなりません。国公立大学であれば学費が低めに設定されているため、年収600万円程度でも進学費用を賄うことが可能ですが、それでも家計に余裕を持たせるための計画性が求められます。
また、教育費以外にも住宅ローンや老後資金など、他の支出項目も家計に影響を与えるため、トータルで収支のバランスを考えることが重要です。
大学無償化制度と収入の関係
大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)は、家庭の年収が一定の基準以下である場合に、学費や生活費の負担を大幅に軽減する制度です。この制度の対象となるのは、住民税非課税世帯やそれに準じる収入の家庭です。
具体的には、世帯年収が約270万円以下の場合、国公立大学の授業料が全額免除され、さらに生活費として給付型奨学金が支給されます。私立大学の場合でも、授業料の一部が免除され、一定の給付型奨学金を受け取ることが可能です。この制度を活用することで、低収入の家庭でも大学進学が現実的な選択肢となります。
ただし、制度の対象外となる年収約600万円以上の家庭では依然として費用負担が重く、奨学金の利用や家計の見直しが必要です。
家計と進学を両立させるプランニングができれば270万円以下でも大学進学は可能
大学進学には大きな費用がかかりますが、奨学金や大学無償化制度を適切に活用することで、家計への負担を軽減することは可能です。奨学金を利用する場合は、卒業後の返済計画を立てることが重要であり、利用しない場合は家計に余裕を持たせる収入が必要です。
また、大学無償化制度は低収入世帯にとって非常に有効な手段ですが、中間層家庭には別の資金計画が求められます。将来的な家計負担を見据えた早めの準備と、制度の活用による柔軟な対応が、子どもの夢を支える鍵となるでしょう。
出典
文部科学省 学びたい気持ちを応援します
日本学生支援機構 奨学金制度の種類と概要
文部科学省 令和6年度からの奨学金制度の改正
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

































