息子は社会人2年目で「奨学金」を返済中です。もし返済できなくなった場合、親が「代わり」に支払うことになるのでしょうか?
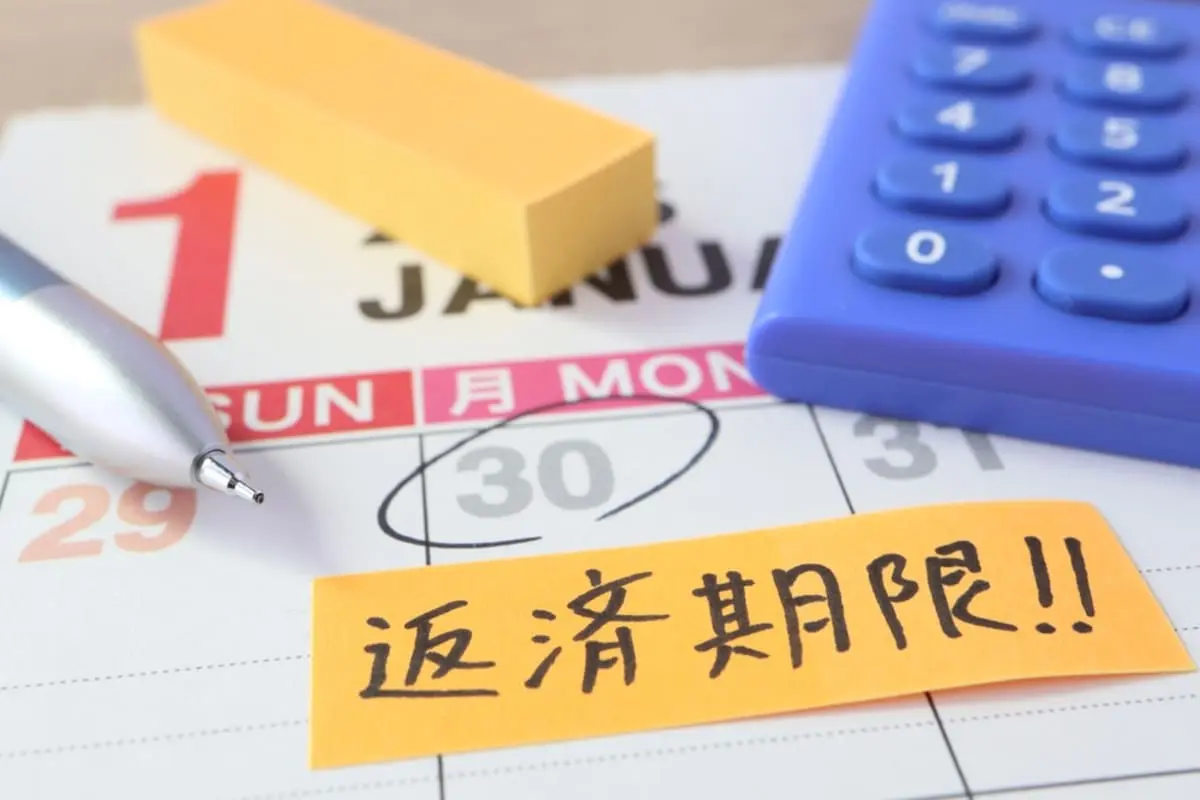
今回は、奨学金の返済が困難になった場合の制度について解説します。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト
金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっています。
どの金融機関にも属さない独立系FPです。
奨学金は親が借りるものなの?
まず、押さえておくべき基本の内容として、奨学金は誰が借りるのかということです。奨学金は、奨学生本人(子)が借りる(国の教育ローンは親が借りる)ものです。
そのため、奨学金の返済義務はあくまでも借りていた奨学生本人が負うことになります。本人の返済が難しくなったからといって、親が返済を肩代わりしなければならないという決まりはありません。
ただ、実際には親が奨学生であった本人に代わって奨学金の返済をすることがあります。その場合は、贈与税の対象になるケースがありますので注意してください。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた合計額から基礎控除額である110万円を控除した金額に課されます。つまり、110万円までは非課税となり、110万円を超えたときには贈与税が課されることになるのです。
また、親の扶養に入っていても奨学金返済が生活費や教育費と認められなければ、課税対象となってしまいます。
返済が困難になったときにとるべき行動とは
日本学生支援機構の奨学金の返済が困難になった場合、月々の返済を軽くする「減額返還制度」と返還を待ってもらう「返還期限猶予制度」があります。
~減額返還制度~
減額返還制度とは、災害、傷病、その他経済的理由で奨学金の返還が困難な奨学生本人で、当初約束した割賦金を減額すれば返還可能である人が対象です。返還する方法は、当初の返還月額を一定期間減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長するという方法です。
ただし誰でも利用できるわけではなく、一定の要件をクリアできなければ利用できません。また、1回の申し出につき適用期間は12ヶ月、最長15年(180ヶ月)まで延長できます。
~返還期限猶予制度~
返還期限猶予制度とは、災害、傷病、経済困難、失業など、返還が困難な事情が生じたとき、返還の猶予を願い出ることができる制度です。
そのような状態になったときには、すみやかに手続きすることが大切です。延滞をさせないことが大切です。
返還期限猶予制度を願い出ると、審査により承認された期間の返還は必要がなく、適用期間が経過すると返還が再開される仕組みです。また、その期間に応じて返還終了年月も先送りされます。ただし、申請が承認されない場合は、返還し続けなければなりません。
返還が免除されるケースもある
奨学金は返還しなければなりませんが、一定の状態にあったときには願い出ることにより、返還未済額の全部もしくは一部の返還を免除することが可能となる制度があります。
返還が免除されるのは、(1)本人が死亡し返還ができなくなったとき、(2)精神または身体の障害により労働能力を喪失、もしくは労働能力に対し高度の制限があり、返還ができなくなったときの2つのケースです。
(1)本人が死亡し返還ができなくなったとき
下記2つの書類の提出が必要です。
・貸与奨学金返還免除願または給付奨学金返還免除願
(相続人、連帯保証人連署。機関保証制度加入者および給付奨学金対象者は相続人のみ)
・本人死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明または住民票等の公的証明書(コピー不可)
(2)精神または身体の障害によって労働能力を失う、もしくは労働能力に対し高度の制限があり、返還ができなくなったとき
下記3つの書類の提出が必要です。
・貸与奨学金返還免除願または給付奨学金返還免除願をA3用紙に印刷して提出
(本人、連帯保証人連署。機関保証制度加入者および給付奨学金対象者は本人のみ)
・返還することができなくなった事情を証明する書類(コピー不可)
・診断書(日本学生支援機構所定用紙)
A3用紙に印刷の上、病院の封筒に封入し密封してから提出。開封厳禁。封筒が密封していない状態で提出されたときには不受理となり、再度、診断書の取得が必要です。
免除制度があるといっても、個人で判断するのは難しいものです。返済が難しくなったなら、できるだけ早く借入先に申し出ることが大切です。その際には免除できるのか、できない場合には返済額や返済期間の変更は可能か等を相談しましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
独立行政法人日本学生支援機構 返還が難しくなった場合
執筆者:飯田道子
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト

































