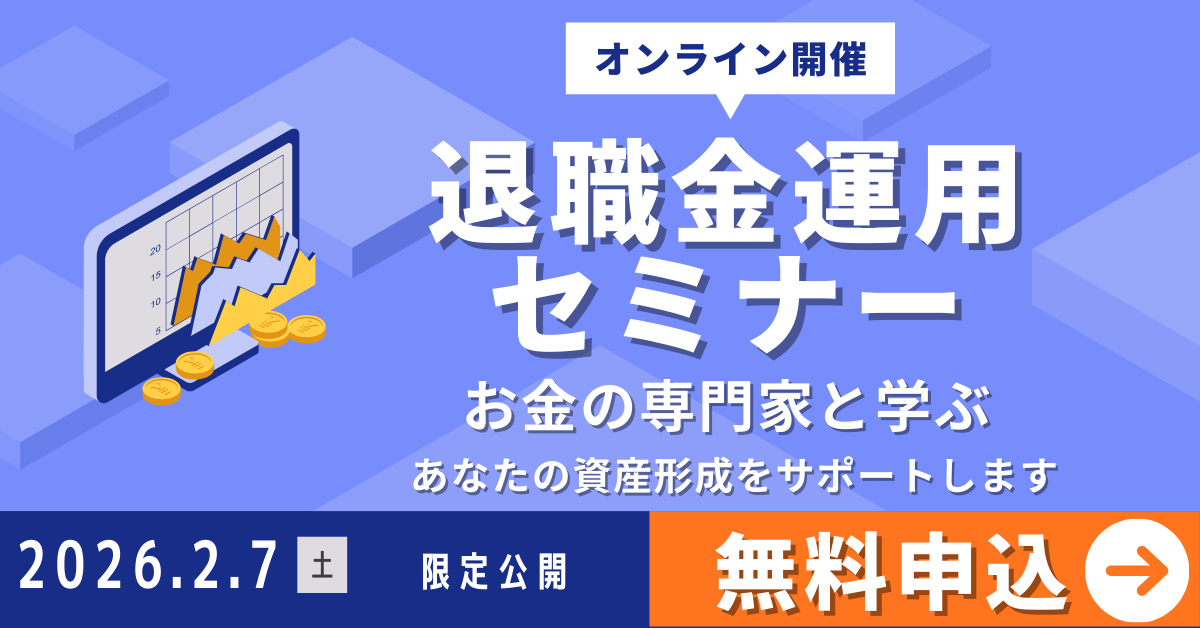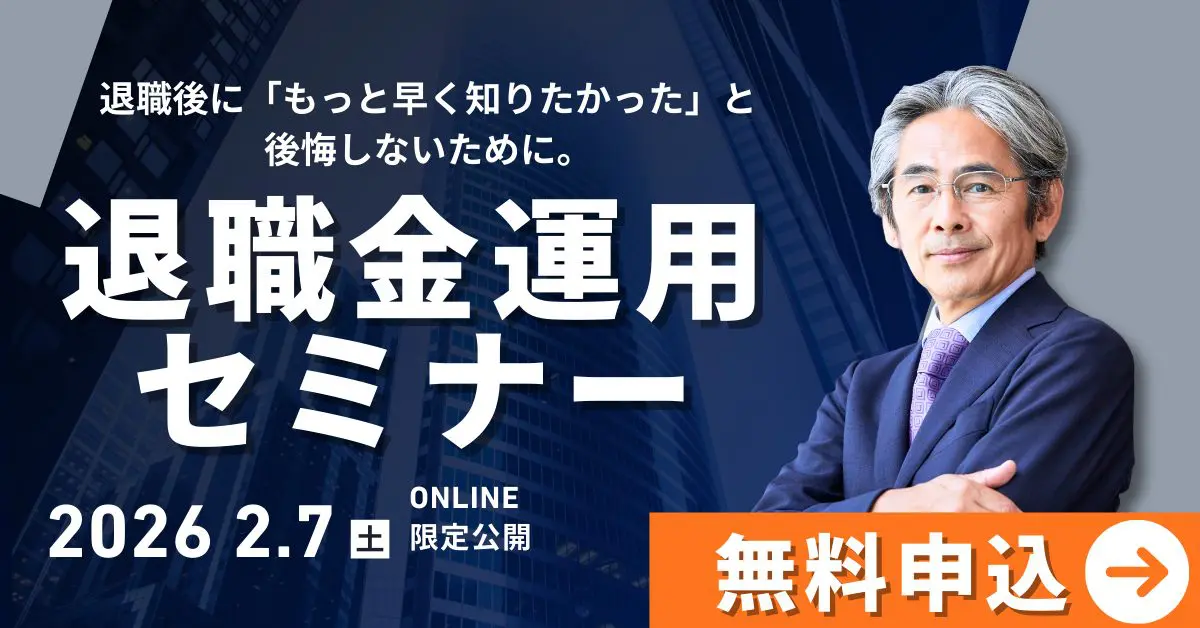【退職前に要チェック】「退職日」が1日ずれるだけで受け取れる退職金が違う!?

退職する前に、退職金の金額と退職所得控除額をチェックしておきましょう。本記事では、退職日を1日遅くするだけでもらえる金額が増える可能性があることを、例を挙げて説明します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも
【PR】イエウール
退職金には非課税枠がある! 退職所得控除額の計算方法
退職金には「退職所得控除額」という非課税枠があり、勤続年数の長さに応じて多くなります。退職所得控除額の計算方法は以下の通りです。
【勤続年数20年超】
・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
【勤続年数20年以下】
・40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合は80万円)
例えば22歳から60歳まで38年間にわたって勤めてきた場合、退職所得控除額は以下の通りです。
・800万円+70万円×(38年-20年)=2060万円
退職金が2060万円を超えない場合、課税されることはなく額面通りを受け取れます。しかし2060万円を超える場合は、超えた部分の2分の1が退職所得の金額となり、これに所得税と住民税が課税されます。
退職日が1日ずれるだけでもらえる金額が異なるケースとは
勤続年数は1年未満の端数が切り上げとなり、1日だけでも1年としてカウントされる点に注意が必要です。
勤続年数が38年と1日の場合は勤続39年となり、退職所得控除額も800万円+70万円×(39年-20年)=2130万円です。非課税枠である退職所得控除額は、勤続年数が1年多くなると70万円増えることになります。
例えば1987年4月1日に入社した人が、2025年3月31日に退職すると勤続38年になりますが、2025年4月1日に退職すると勤続39年となり、非課税枠が70万円増えることになります。
いずれの場合も、退職金が退職所得控除額を超えない場合は問題ありませんが、退職金が多い場合はもらえる金額も異なるため注意が必要です。
退職金2500万円と仮定して退職所得をシミュレーション
課税対象となる退職所得の金額は、以下の計算式で算出します。
・(収入金額-退職所得控除額)×1/2
※収入金額は源泉徴収される前の金額
退職金が2500万円と仮定して、勤続38年と39年の場合の退職所得を計算してみると、以下の通りです。
【勤続38年】
・退職所得の金額:(2500万円-2060万円)×1/2=220万円
【勤続39年】
・退職所得の金額:(2500万円-2130万円)×1/2=185万円
退職金2500万円の場合で計算してみたところ、勤続39年のほうが勤続38年よりも退職所得が35万円少なくなるため、所得税や住民税を引いた後の手取り金額が多くなることが分かります。
【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!
【PR】イエウール
退職金が退職所得控除額を超える場合は退職のタイミングに注意
退職金には、退職所得控除額という非課税枠がありますが、それ以上の金額をもらう場合は課税対象となる退職所得が発生し、手取りの金額に影響を与えます。退職所得控除額は勤続年数に応じて増え、勤続年数は1年未満の端数が切り上げとなる点に注意が必要です。
例えば退職金2500万円の場合、勤続38年では退職所得が220万円であるのに対し、勤続39年では185万円となり、課税対象の金額が少なくなります。
退職金を多くもらえる会社に勤めている方は、退職金の金額と退職所得控除額を確認して、退職所得を計算してみるとよいでしょう。退職のタイミングによっては勤続年数が1年多くなり、退職所得控除額が増えて手取り金額にも差が出るかもしれません。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
国税庁 退職金と税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー