貯金が「300万円」なのに、60歳で定年を迎える父。定年後も働くようすすめるべきでしょうか?
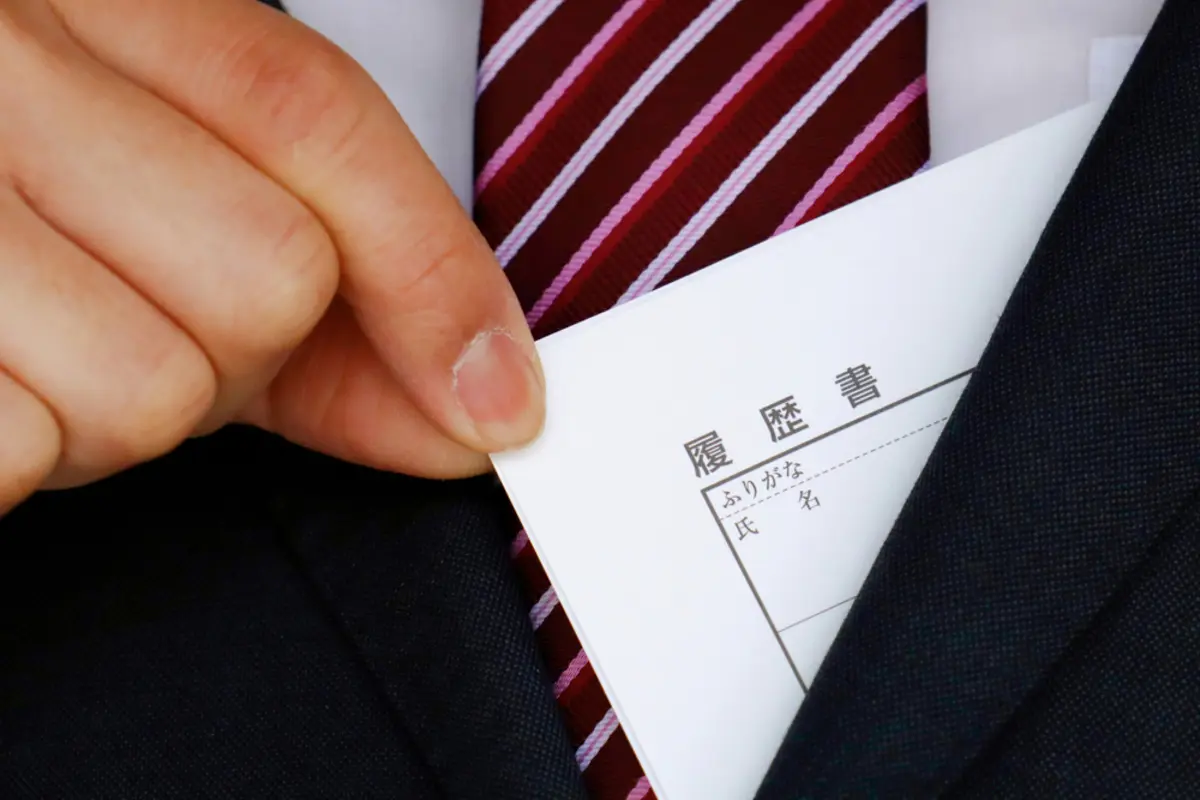
今回は、定年退職後の生活設計について、60歳以降に必要なお金から考えてみました。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも
【PR】イエウール
60歳以上の生活費はいくら必要?
総務省統計局の「家計調査 家計収支編(2022年)」のデータによると、60歳~64歳における1ヶ月あたりの消費支出は以下の通りです。
●二人以上勤労者世帯:約31万2000円
●二人以上無職世帯:約28万7000円
●単身世帯:約15万円
※単身世帯は60歳以上の平均消費支出
※いずれも税金などの非消費支出を含めない
もちろん、各世帯によって支出の内容や金額はそれぞれ異なりますので、目安として覚えておきましょう。
60歳から年金を受給する方法
仮に60歳で定年退職し、その後再雇用などの制度を利用せず無職になるケースを考えてみます。
一般的に、退職後とくに収入源がない場合、定年退職後の主な収入の中心となるのは年金です。年金は現在、原則として65歳から受給開始となっています。そのため、60歳から年金を受給する場合は「繰上げ受給」の制度を利用することになります。
繰上げ受給をすると年金が減額され、60歳から受け取ると最大24%(昭和37年4月1日以前生まれの方は最大30%)の減額率となり、その後も減額された金額が支給されるため、注意が必要です。
厚生労働省年金局の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、60歳から受給する厚生年金の平均月額は男性が9万6583円、女性が8万4623円です。収入源が厚生年金のみだとすると、家計調査のデータにおいて最も支出額が少ない単身世帯で計算しても、月に5万円以上足りません。
今回のケースの場合、貯金の300万円を少しずつ取り崩して不足する生活費に充てると、およそ5年で貯金が底をついてしまうことになります。
【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!
【PR】イエウール
定年退職後の生活をどうするか考える
定年退職した後、繰上げ受給する年金だけで生活していくのは難しいといえるでしょう。生活費の不足分を補うために貯金は目減りしていくのに加え、もし突発的に大きな出費が発生することになっても、払えない可能性が高くなります。
貯金が少ない場合、健康面や体力に問題がなければ、子どもは親に定年退職後も引き続き働くことを検討してもらうか、生活費をサポートすることが必要となるでしょう。
継続して働くことを考えてもらう
本人の意志や意欲を尊重する必要がありますが、再雇用制度などを利用して継続して働くことを考えてもらいましょう。
現在は「高年齢者雇用安定法」という法律で、企業は「定年を65歳まで引き上げる」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかを取り入れることが義務化されています。
さらに定年を70歳まで引き上げる努力義務もあわせて制定されており、60歳以降でも意欲があれば、働き続けられる環境が以前よりも整ってきているといえるでしょう。
内閣府が公開している2022年のデータをみると、60歳~64歳の73%、65歳~69歳の50.8%、70歳~74歳の33.5%、75歳以上の11%が何らかのかたちで就労しています。
再雇用の場合、仕事内容や給与などは保証されていないため、給与が下がる可能性は高くなりますが、多くの人が60歳を過ぎても働いていることを知ってもらうと、働くことをすすめやすくなるでしょう。
子どもがサポートする
場合によっては、子どもが金銭的に援助することも考える必要があります。
厚生労働省の「令和4年 国民生活基礎調査」によると、親へ仕送りをしている世帯は全体の2%ほどです。
1世帯あたりの仕送りは、1ヶ月あたり2万円~4万円未満、年代別では50歳~59歳が最も多くなっています。子どもが親を金銭的にサポートする場合は、自分の生活に無理のない範囲で行うことが大切です。
働かない場合、300万円の貯金は底をつく可能性が高い。できれば働き続けることをすすめる
貯金が300万円の場合、60歳で定年退職しその後収入がないと、支出を切り詰めても数年で貯金がなくなる可能性が高くなります。
本人の意志を確認する必要がありますが、できれば60歳以降も引き続き働いてもらうようにして、収入を増やすとマイナス分をカバーできるでしょう。
以前よりも、60歳以降も働きやすい環境は整ってきているといえます。一定の収入があることで、老後の生活における安心感は高まるでしょう。
出典
e-Stat 政府統計の総合窓口 総務省統計局 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 2022年 第3-2表 世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出
e-Stat 政府統計の総合窓口 総務省統計局 家計調査 家計収支編 単身世帯 2022年 第2表 男女、年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出
厚生労働省 令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 II 厚生年金保険(2)給付状況 表12 厚生年金保険(第1号) 老齢年金受給権者状況の推移(男子)(12ページ)、表13 厚生年金保険(第1号) 老齢年金受給権者状況の推移(女子)(13ページ)
e-Stat 政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和4年国民生活基礎調査 世帯 表番号61 06 仕送りの状況 世帯数-1世帯当たり平均仕送り額,仕送り有-仕送り額階級-無・仕送りの種類(複数回答)・世帯主の年齢(10歳階級)別
内閣府 令和5年版高齢社会白書(概要版)第2節 高齢期の暮らしの動向 図1-2-1 年齢階級別就業率の推移(4ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー


































