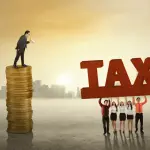青色申告で「65万円」の控除をするにはどうしたいい?雑所得と事業所得、どちらが有利なのでしょうか?


サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。
現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。
ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。
FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。
2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。
現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。
早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。
サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow
【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも
【PR】イエウール
年金生活者が仕事を始める動機と理由
年金を受け取りながらアルバイトや新たに事業を開始したり、退職後のセカンドキャリアとしてビジネスを始めたりするケースは増えています。
また高齢化社会においては、年金だけでは生活費が十分でない方や、社会とのつながりや生きがいを得るために事業を行う方も少なくありません。
年金生活者が仕事をするメリット
1. 収入の増加
年金受給だけでは生活費が足りない場合、給与所得や事業所得を得ると、家計が潤うという大きなメリットがあります。特に、国民年金のみの方や、厚生年金でも受給額が十分でない場合には、給与所得や事業所得が生活を支える大きな助けとなります。
2. 社会参加・自己実現
事業を行うことで、社会とのつながりを維持し、自己実現や生きがいを得られるという、精神的なメリットがあります。人との交流やビジネス上のチャレンジが、健康や意欲を保つきっかけにもなります。
3. 節税効果の可能性
事業所得として認められれば、必要経費を差し引いて課税所得を計算できます。
例えば、事業に直接関連する経費(事業用の通信費や交通費、仕入れ費用など)を経費計上することで、所得税の負担を抑えることができる場合があります。事業所得や雑所得として認められた場合、事業でいくら稼いでも、年金を減額されることはありません。
それに対し、雇用契約を結び給与所得者となった場合は、後述するように「在職老齢年金」の支給停止の対象になる可能性があるので、注意が必要です。
【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!
【PR】イエウール
年金生活者が仕事をするデメリットと注意すべき点
1. 年金額への影響(在職老齢年金制度)
年金生活者が給与所得と年金を同時に受け取ると、年金が一部停止・減額される「在職老齢年金」の支給停止対象となる場合があります。
ただし、国民年金や基礎年金は支給停止の対象にならず、報酬比例部分の年金を150万円とすると、給与収入が450万円までなら年金は支給停止されないので、大きく稼がないかぎり心配はいりません。
2. 税金や社会保険料の増加
事業所得が増えれば、その分所得税や住民税が増えます。また、国民健康保険料は所得に応じて算出されるため、事業所得が増えると保険料負担も大きくなる可能性があります。
3. 事務作業やリスクの増加
事業を行うためには、帳簿の作成・経理処理・確定申告などの事務作業が必要となります。青色申告にすると節税メリットはありますが、複式簿記で帳簿を付ける必要があり、慣れない方には負担が大きいかもしれません。また、商売がうまくいかないリスクも念頭に置く必要があります。
4. 適切な所得区分
事業として継続的・独立的に営利活動を行っている場合は「事業所得」、趣味的・副業的性格が強い場合は「雑所得」と判断される可能性があります。いずれも年金の支給停止の対象にはなりませんが、事業所得なら青色申告が可能になり、節税メリットも期待できます。
青色申告を行うには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、複式簿記で所定の帳簿を作成・保存する必要があります。青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰越などの優遇がありますが、提出期限を過ぎるとその年は青色申告ができないことに、注意が必要です。
5. 体力・健康面の管理
高齢期に事業を行う場合、体力や健康面を考慮しながら無理のない範囲で続けることが大切です。事業規模が大きくなりすぎると、過度のストレスや健康への悪影響が生じる可能性があります。事業計画を立てる際は、長期的な見通しも含めて検討する必要があります。
まとめ
年金受給者が事業を行うことは、収入増や生きがいの面で大きなメリットがある一方、年金額の減額リスクや増税、事務負担などのデメリットも生じます。特に、在職老齢年金制度の適用や所得税・住民税・社会保険料の増加などは、事業規模や所得額によって影響が異なるため、事前の情報収集が必要です。
もし事業として本格的に展開するのであれば、青色申告の活用や適切な経理処理を行い、節税とトラブル回避を図るべきです。また、年齢や健康状態を踏まえ、過度なリスクを避けながら、楽しみと収入を両立させることを目指すのが理想的でしょう。
出典
日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度)
国税庁 No.1300 所得の区分のあらまし
国税庁 No.2070 青色申告制度
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー