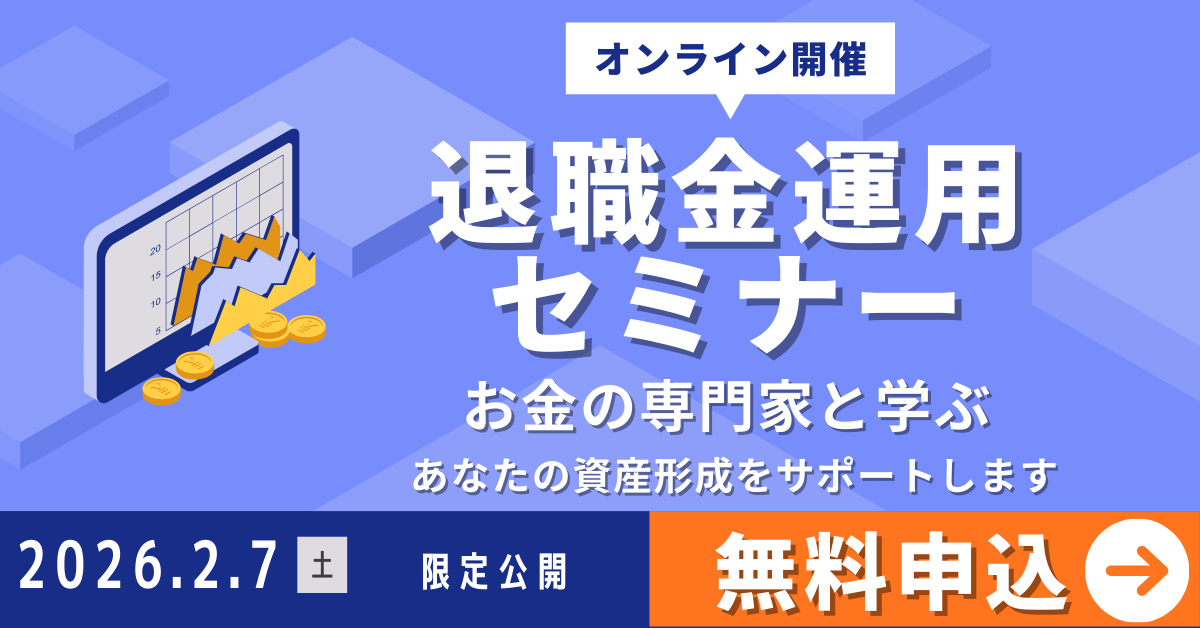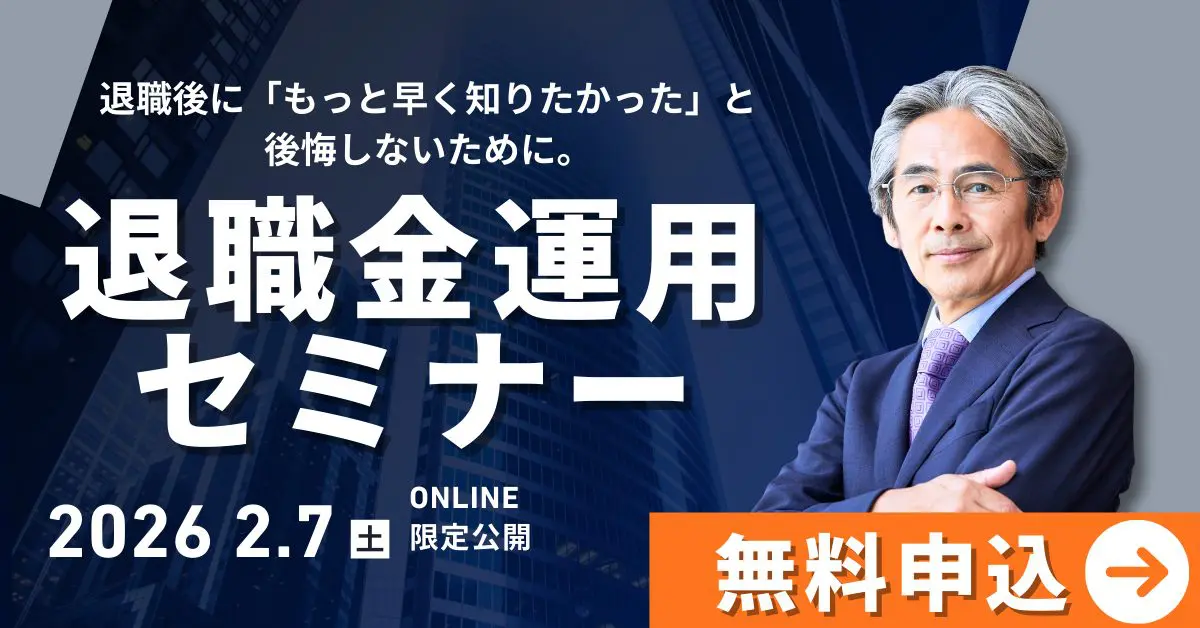60歳で退職して年金を65歳でもらうと、5年間「無収入」になりますよね?どうやって過ごしたらいいのでしょうか?

そこで本記事では、5年間に必要な生活資金の目安や生活資金を確保するための方法などを解説します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも
【PR】イエウール
60~65歳の5年間に必要な生活資金
総務省の家計調査報告では、65歳以上の単身無職世帯における支出額の平均が公表されています。本記事のタイトルに関係する、60~65歳までの支出額ではありませんが、参考にはなるでしょう。
同調査によると、65歳以上の単身無職世帯における消費支出額の平均は月額で14万5430円です。また、直接税や社会保険料が含まれる、非消費支出額の平均は月額で1万2243円となっています。
つまり、65歳以上の単身無職世帯における、1ヶ月当たりの平均支出額は15万7673円です。1年当たりでは189万2076円となり、5年間生活するためには946万380円が必要になるといえます。
ただし、この試算は平均額を基準にしたものです。実際にかかる支出額は、生活水準などによって異なるでしょう。その支出額が平均よりも多ければ、5年間生活するために必要な金額も増大します。無論、その逆も然りです。
退職から年金支給までの生活資金源
定年退職のタイミングは人それぞれですが、最短で60歳です。対して、年金を受け取れるのは原則65歳からです。なお、繰上げ受給を行うことで60歳から年金を受け取れますが、受給額は減額されます。
60歳で定年退職し、65歳で年金を受け取り始めるまでの5年間の生活資金源として、まず候補に挙がるのは退職金の利用です。退職金の金額は人それぞれですが、生活資金として必要な金額の基準は前述した約946万円です。
会社によっては、退職金制度を導入していないこともあります。そのため、退職金制度の有無も含めて、可能であれば受け取れる退職金の金額を会社側へ確認しておくといいでしょう。退職金や貯蓄などで生活資金を賄えない場合は、60歳以降も働いて収入を得ることが解決策の一つです。
定年退職後の働き方として、再就職と再雇用があります。
再就職
再就職とは定年を迎えて退職したあとに、それまで勤めていた会社とは別の会社に就職することです。自分で就職先を探す必要があるため、転職のイメージに近いでしょう。
再雇用
再就職に対し、再雇用とは会社の再雇用制度を利用して、それまで勤めていた会社で引き続き働くことを指します。この場合、一度退職したあとに、再度雇用契約を結びます。
ただし、雇用形態などの契約内容が定年退職前と異なることも少なくありません。なお、再雇用後に必ずしも定年退職前と同じ職場で働くとは限らず、子会社やグループ会社での勤務になることもあります。
【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!
【PR】イエウール
定年退職後も働くメリットとデメリット
定年退職後も働くメリットは以下の通りです。
●安定した収入を得られる
●経験やスキルを仕事に生かせる
●人との関わりを持てる
●健康維持に繋がる
●要件を満たせば、社会保険に加入できる
定年退職後も働く最大のメリットは、継続的に安定した収入を得られる点にあるでしょう。生活資金に不安を感じている方にとっては、特に重要なメリットといえます。
仕事を退職すると、社会や他人との関わりが減ってしまう方は少なくありません。仕事を続けることで、他人と関わる機会を維持できます。
対して、定年退職後も働くデメリットは以下の通りです。
●心身に負担がかかる
●現役時代と比較して、給料が低くなる可能性がある
●趣味などに使う自由時間が取りにくい
高齢になると、体力や気力が低下することが一般的です。定年退職後も働くことは身体や頭の運動になり、健康維持につながる可能性がある一方で、負担にもなりかねません。
働く際の契約内容次第ではありますが、現役時代と比較して給料が低下することもあります。人によっては、年収の低下が働く際のモチベーションに深く関わるかもしれません。
働くことも一つの選択肢
定年退職の最短は60歳ですが、年金を受け取れるのは原則として65歳からです。その5年間の生活資金源として、まず候補に挙がるのは退職金です。ただし、退職金や貯蓄を利用しても生活資金に不安が残る場合は、定年退職後も働いて収入を得ることが選択肢の一つになるでしょう。
働き方は主に、再就職と再雇用があります。再就職は転職という形で、それまでの会社とは別の会社に就職して働きます。再雇用はそれまで勤めていた会社と再度雇用契約を結び、働くことを指します。
出典
総務省 家計調査報告〔家計収支編〕2023年(令和5年)平均結果の概要(19ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー