年金を繰下げると最大で「84%」増える? 最大まで繰下げて増額した場合と、65歳から受け取り始めた場合では、どちらが最終的にお得なのでしょうか?
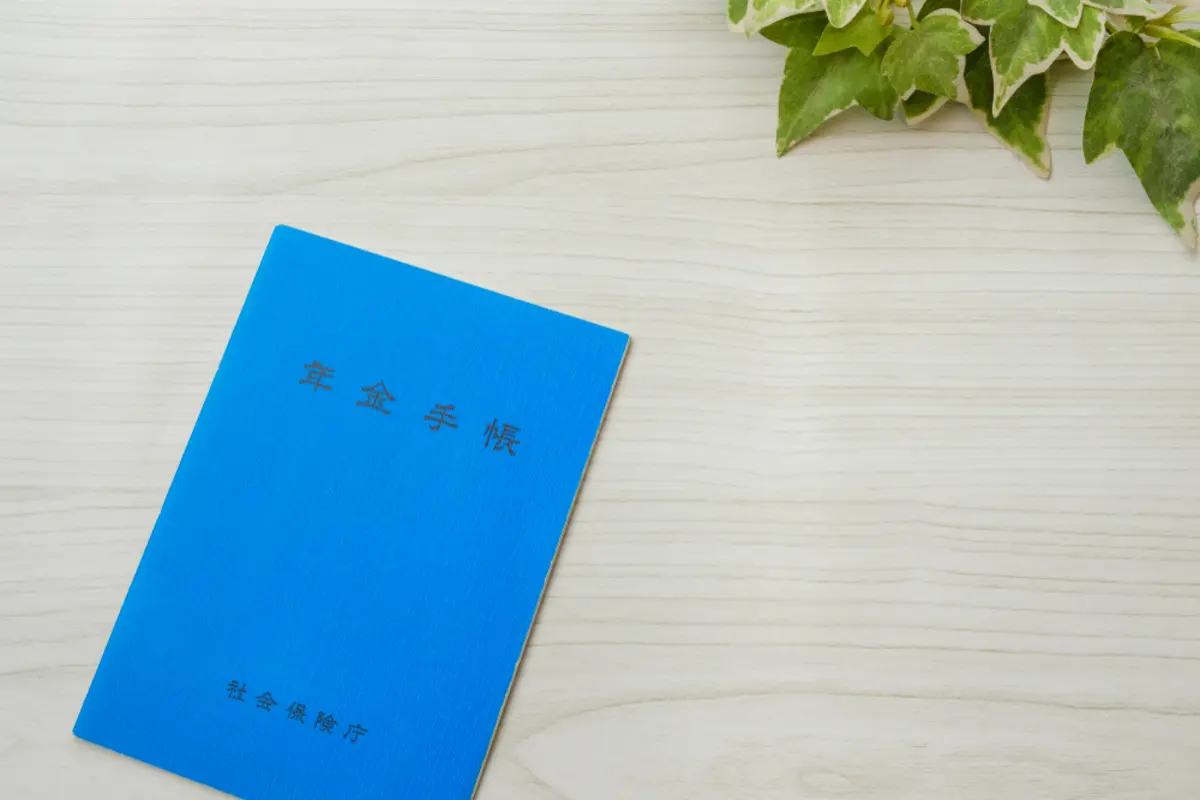
人間の寿命は誰にも予測することはできないため、繰下げる場合とそうでない場合、どちらが最終的に「お得」となるかの判断をすることはできません。
このことを踏まえつつ、本記事では、増額される年金額の目安や繰下げ受給を選択する際の注意点などについて、確認していきます。

ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
ズバリ、損益分岐点は「プラス11.9年」
ご承知のとおり、公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の受給開始年齢は、原則65歳からとなります。本記事では詳細な説明は割愛しますが、年金を60歳から65歳までの間に早く受給できる繰上げ受給も選択することができます。
繰下げ受給では、66歳から75歳までの間に受給開始時期を遅らせることで、年金額が1月当たり0.7%ずつ増額され、生涯増額された年金額を受給することができるようになります。
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
例えば、1年(12月)繰下げた場合は、8.4%(=0.7%×12月)の増額率で年金額を増やすことができます。75歳まで最大に繰下げた場合には、8.4%×10年で84%の増加率となります。
ただし、繰下げている期間は年金を受け取ることができないため、他の資金(退職金、給与収入、預貯金等)で生活費などを賄う必要があります。手元の資金が潤沢であれば特に問題はないと思われますが、年金を老後資金の中心として考えていた場合には、受給開始時期の選択は特に重要となるでしょう。
単純に受給開始年齢を65歳とした場合と、一定年齢繰下げした場合の損益分岐点は、ズバリ、受給を開始した年齢プラス「11.9年」となります。
例えば、70歳まで5年間繰下げたケースを考えてみましょう。このとき、65歳時点での年金額を100%とすると、70歳から受給できる年金額は100%+8.4%×5年=142%となります。70歳までの間の5年間は年金を受け取っていないため、その分(100%×5年分)を増加率42%で割った数値でトントン(損益分岐点)となります。
100%×5年÷42%=11.9年(70歳から11.9年後にトントン)
このように、繰下げ受給の場合は、繰下げた受給開始年齢から11.9年(おおむね干支一回り)以上生きて年金を受給できれば、それ以降は65歳で受給開始したときよりもお得になると考えられます。
繰下げ受給を選択する際の注意点
ほかにも、公的年金の受給に関して覚えておきたい注意事項があります。
1.老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは別々に選択できる
厚生年金の加入期間があった人(会社員や公務員等)は、一定の条件を満たすと老齢厚生年金を受給することができます。
その場合に、老齢基礎年金とは別々に繰下げ受給を選択することができます。ちなみに、繰上げ受給については両者を同時に受給開始する必要があります。
2.税金や社会保険料の負担が増加する場合がある
当然ながら、年金額の増額により収入が増えるため、その分の所得税等、住民税の税金負担や社会保険料の負担などが増加するケースがあります。
3.医療費の負担額が増加する場合がある
例えば、後期高齢者(75歳以上)の医療費負担は、原則1割負担(窓口負担)とされていますが、年収により2割負担(一定以上所得がある方)、3割負担(現役並み所得がある方)となる場合があります。
4.加給年金が受給できない
加給年金とは、会社員等で厚生年金の加入期間が20年以上ある人に、配偶者(65歳未満)または子(18歳到達年度の末日までの子など)がいるときに加算される、扶養手当のような年金のことです。残念ながら、繰下げしている期間については加給年金を受け取ることはできません。
ちなみに、令和6年度においては、配偶者分として23万4800円(配偶者加給年金額の特別加算額も含めると40万8100円)の年金が受給できます。もし、繰下げている間に配偶者も65歳となってしまうと、1円も受給することができません。
まとめ
前述のとおり、人間がいつまで生きられるかを予測することは難しいため、「お得になる」との表現は適切ではないのかもしれません。最近では、特に若い年齢層の方々を中心に、将来受け取る年金額に過度に期待しない風潮もあるように思われます。
その分、若いうちから、NISAやiDeCoなどの制度を活用した投資による老後資金の確保や、保険、貯蓄などによる準備をしっかりと始めている人も多いのではないでしょうか。参考程度でも結構ですので、繰下げ受給の損益分岐点は「干支一回り」程度と覚えておきましょう。
出典
日本年金機構 年金の繰下げ受給
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

































