定額減税で低下した「税金」や「社会保険料」の国民負担率。低下しても45.8%のようですがこれって高くないですか?
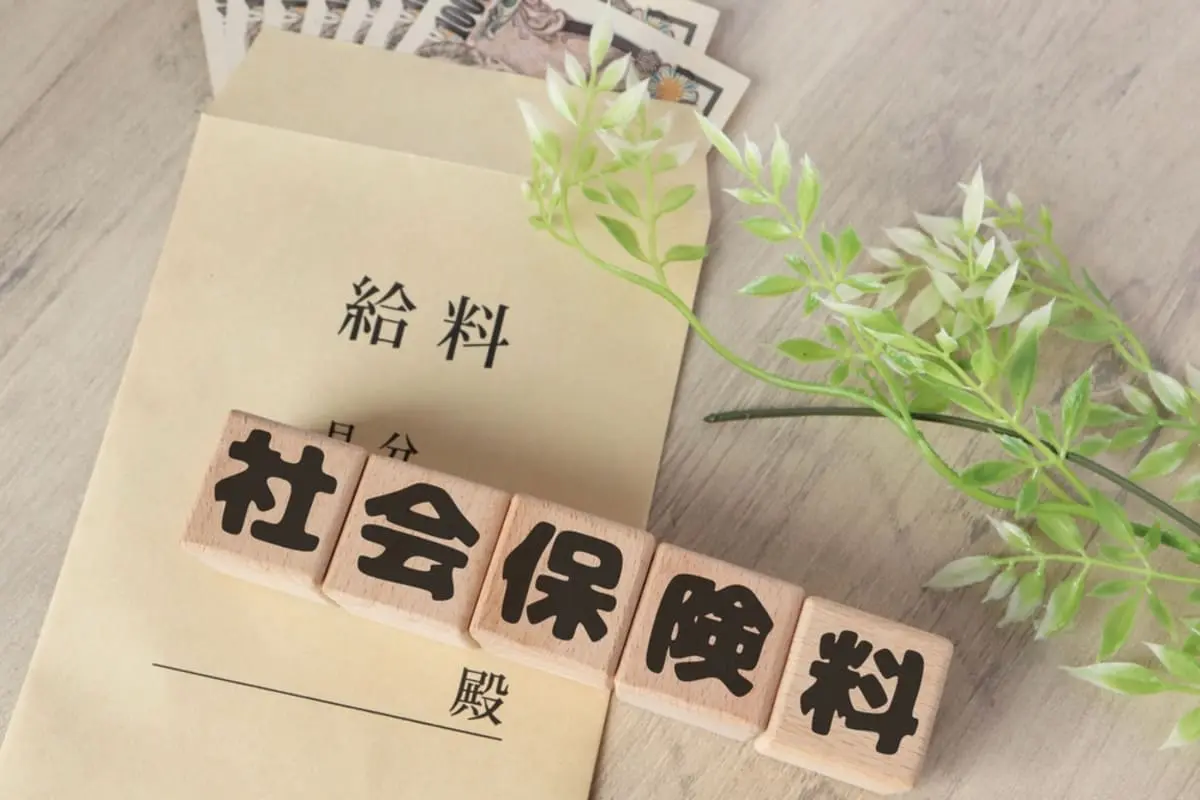
財務省の公表によれば、令和6年度の国民負担率実績見込みは45.8%とされていますが、果たしてこの負担率は妥当なのでしょうか。また他の国と比べて高いのでしょうか。本記事で分かりやすく解説します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
国民負担率とは? その計算方法と最新の数値
国民負担率とは、国民が税金や社会保険料として負担する金額の、国民所得に対する比率を示す指標です。具体的には、租税負担率と社会保障負担率を合計したものを指します。
この指標は、国民全体の経済的な負担感を測るために用いられます。財務省によると、令和6年度の国民負担率の実績見込みは45.8%となるようです。前年度の46.1%から0.3ポイント減少しており、これは定額減税の影響によるものと考えられます。
定額減税がもたらした国民負担率の変化
令和6年度に実施された定額減税は、国民負担率の低下につながりました。具体的には、納税者とその配偶者を含む扶養親族に対して、所得税3万円、個人住民税1万円の減税が行われました。財務省によれば、国民負担率45.8%の内訳は以下のとおりです。
●国税:17.5%
●地方税:10.1%
●社会保障負担:18.3%
これらの内訳から、社会保険料の負担が最も大きいことが分かります。ただし、国民負担率には個人が直接負担するものだけでなく、法人税や企業が負担する社会保険料も含まれています。
日本の国民負担率は高い? 国際比較で見る位置づけ
国民負担率が45.8%という数値は、国際的に見てどのような位置づけにあるのでしょうか。
財務省の資料によれば、日本の国民負担率は主要先進国と比較して中程度の水準に位置しています。例えば、2022年のデータでは、フランスは68.1%、ドイツは55.9%、スウェーデンは55.5%と、日本より高い数値です。
これらの国々は、高い国民負担率に見合った手厚い社会保障制度を提供しているとされています。特に北欧諸国は、高負担・高福祉で知られ、医療や教育が基本的に無償で受けられるなど、国民全体に対して充実した福祉サービスを提供しています。
一方、アメリカの国民負担率は36.4%と日本より低い水準にありますが、その分、社会保障制度は限定的で、特に医療費が非常に高額であるといわれています。例えば、日本では盲腸(虫垂炎)の治療費は40万~60万円程度(3割負担の場合12万~18万円程度)ですが、アメリカでは300万円以上かかるケースもあるようです。
このように、国民負担率の高さは、各国の社会保障制度の充実度と密接に関連しており、高い負担率の国ほど、医療や教育、福祉サービスが手厚い傾向にあります。
将来の国民負担率と私たちの生活への影響
今後の国民負担率は、社会保障費の増加や経済成長率など、さまざまな要因によって上昇する可能性があると考えられます。これにより可処分所得が減る一方で、社会保障制度の維持や公共サービスの充実につながる側面もあります。
私たち一人ひとりが税金の使い道や社会保障のあり方に関心を持ち、持続可能な社会の実現を目指すことが重要です。
出典
財務省 令和7年度の国民負担率を公表します
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

































