子どものお迎えのために「時短勤務」にしたのに、上司に「残業できないの?」と言われます。忙しい中で帰りにくいですが、断っても問題ないですよね…?
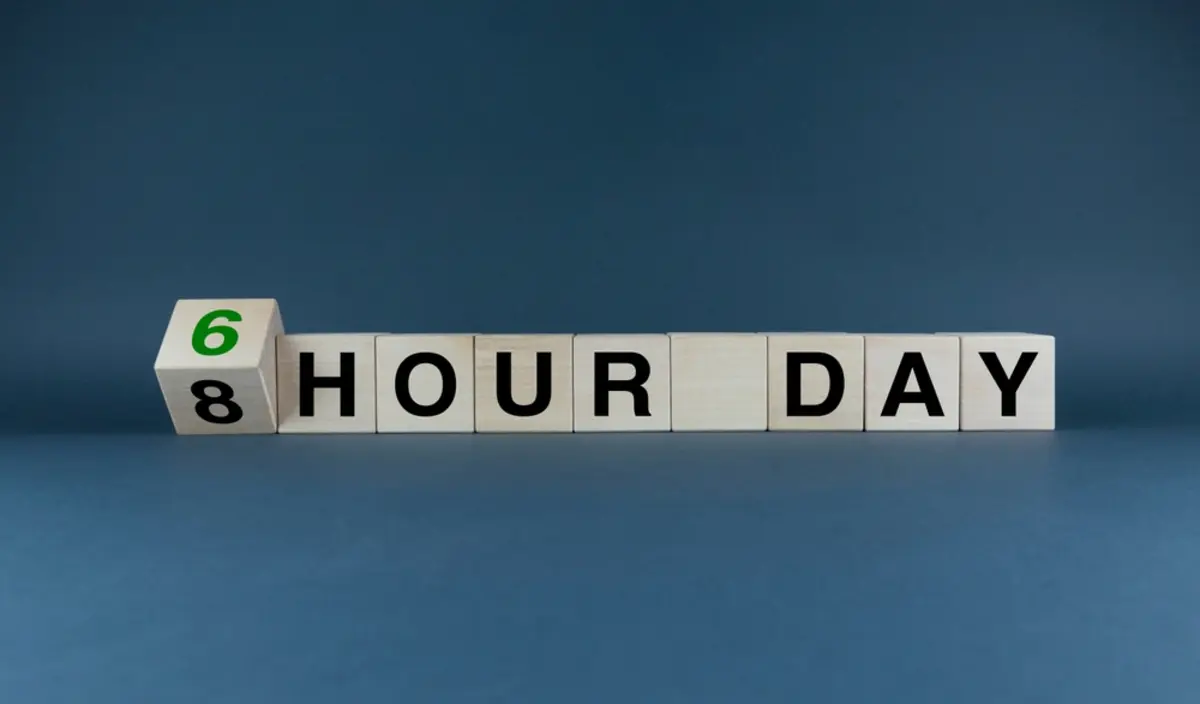
本記事では、時短勤務の仕組みと、子どものお迎えを理由に残業を拒否することができるのかについて解説していきます。残業を拒否することができない場合についても紹介するので、時短勤務をする際の参考にしてください。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
時短勤務が認められる場合
時短勤務とは1日の労働時間を短縮して勤務することで、育児・介護休業法では「短時間勤務制度」として、3歳未満の子どもを養育する労働者が希望を出すことで利用できます。時短勤務は1日の所定労働時間を原則6時間にするもので、子どもの送り迎えに合わせて労働できる制度です。
しかし、時短勤務の対象となるためには要件を満たす必要があります。その主な要件は次の3つです。
●所定労働時間が1日6時間を超えていること
●日雇い労働者ではないこと
●時短勤務期間に育児休業をしていないこと
子どものお迎えを理由に残業を拒否できる?
時短勤務であっても事業主から残業を求められてしまう可能性があります。しかし、この場合は一定の要件を満たす労働者は残業を拒否することが可能です。
具体的には、「3歳未満の子どもを養育する労働者」が所定労働時間内で労働したいことを希望した場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させることができないようになっています。つまり、3歳未満の子どもを養育している労働者であれば、お迎えをするために残業を拒否することも可能です。
残業を拒否できない場合
もっとも、残業を拒否できない場合もあります。
●雇用期間が継続して1年未満であること
●1週間の労働時間が2日以下であること
これらの要件を満たしている労働者の場合です。このような労働者であり、「所定労働時間内で労働したいと希望できない」と労使協定を結んでいると、時間外労働を許容しているので残業を拒否できないことになります。そのため、雇用契約を結ぶ際に、時短勤務を希望できるのか、残業をしないように希望できるのか、について確認するようにしましょう。
また、事業主は「事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけない」(育児・介護休業法第16条の8第 1項)となっているので、「事業の正常な運営を妨げる場合」は3歳未満の子どもを養育する労働者であっても残業を拒否できません。残業することについて、やむを得ない場合があることを覚えておきましょう。
普段から職場内でコミュニケーションを取るようにしましょう
子どものお迎えをするために時短勤務を希望している人も多い中で、残業を頼まれることもあると思います。この場合、3歳未満の子どもを養育しているのであれば、基本的に時間外労働をする必要はありません。残業を頼まれたとしても拒否することができます。
しかし、勤め先が繁忙期である場合や時短勤務によって同僚の負担が大きくなってしまう場合は、残業しないことで気まずい職場になってしまうことも考えられます。そうならないためにも普段からコミュニケーションを取ることが大切です。事業主も時短勤務の労働者が働きやすい環境をつくることを求められます。
また、雇用契約を結ぶ際は雇用契約書や就業規則を確認し、時短勤務や時間外労働の扱いがどのようになっているか確認するようにしてください。
出典
厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー































