父が亡くなり遺産が「500万円」あります。“遺産分割協議”を進めたいのに、参加してくれない人が! 全額「自分のもの」しても問題ない? 対処法を解説
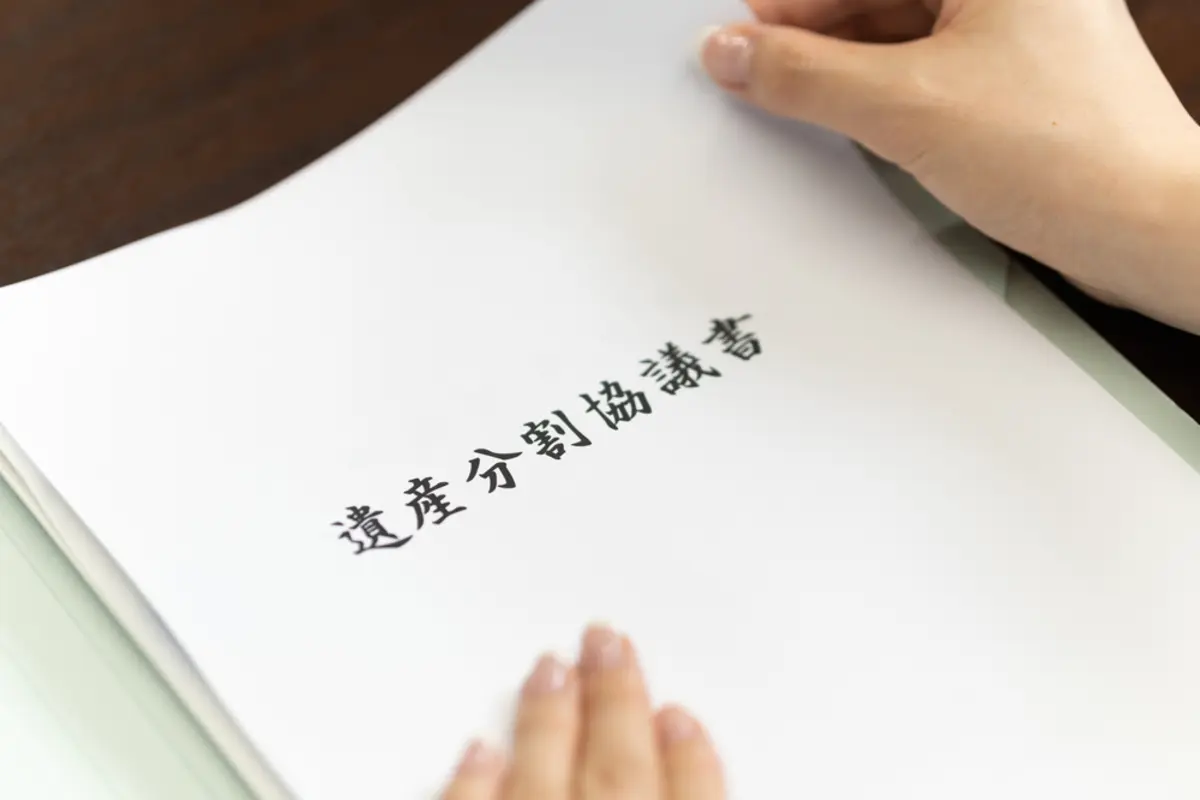
遺産分割協議に参加してくれない人がいるときは、どうすればいいのでしょうか?
本記事では、このようなケースの対策方法などについて解説します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
遺産分割協議に参加してくれない人がいるときはどうする?
遺産分割協議に参加してくれない人がいるときには、参加しない理由について確認することが1つ目です。そもそも遺産に興味がなくて参加しないのなら、相続放棄をしてもらう方法もあります。
しかし、なかには遺産分割せず全額を自分のものにしたいと考えているケースもあるかもしれません。そのような場合でも話し合いを通じて、お互いの考え方や希望などを擦り合わせることが大切です。
大きな問題やトラブルにつなげないためにも、遺産分割協議は参加者全員が納得できる形で進めるようにしましょう。
話し合いでも解決しない場合には、「弁護士に依頼する」「遺産分割調停を起こす」なども方法の1つとなります。ただし、これらの方法は関係性が悪くなるリスクもあります。最も穏便な解決方法は話し合いです。
遺産分割協議は書面として作成する
相続人同士で遺産分割協議をおこない、具体的な相続内容について決めていきますが、相続内容はそれぞれの関係性によって変わり、相続を希望しない場合は相続放棄も可能です。
相続放棄をすると相続人ではなくなるので、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。遺産分割協議の内容はしっかり書面にすることで、後から言った、言っていないの論争を防ぐことが可能です。
遺産分割協議は専門家に相談しながら必要書類をそろえる
遺産分割協議書は、「被相続人の戸籍関係書類」「遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍関係書類」などの書類とともに提出が求められます。ほかにも、相続人全員の印鑑証明書なども必要なので、自分たちだけで判断せず専門家に依頼するのがおすすめです。
遺産分割協議書には全員が内容について納得していることを示すために、相続人全員が印鑑証明書と同じ実印を押さなければなりません。
遺産分割協議は少しでも早く動き始める
遺産分割協議は、少しでも早く動き始めることが重要となります。相続をするときには、相続額に応じた相続税の支払いがあるためです。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(一般的には被相続人が亡くなった日)から、10ヶ月以内に決められている書類を提出しなければなりません。例えば、1月6日に被相続人が亡くなった場合、その年の11月16日が申告期限です。
10ヶ月あるから遺産分割協議を急がなくてもいいと思う人もいるかもしれません。しかし、期限ぎりぎりになってから遺産分割協議をすることには、大きなリスクがあります。
事前に想定した通りに話し合いが進めばいいですが、遺産分割協議に非協力的な人がいたり、そもそも遺産分割に納得していない人がいたりすると、思っているよりも時間がかかることがあります。
このようなケースも頭に入れ、少しでも早いタイミングから話し合いをおこない、仮に問題やトラブルが起きたとしても対応できる時間を確保しておきましょう。
まとめ
遺産相続に際しては、相続人同士で争いになるケースもあるため、遺産分割協議を通じてしっかりと話し合いをするのがおすすめです。遺産分割協議にどうしても参加してくれない人がいる場合は、弁護士への相談や遺産分割調停を起こすことも視野に入れてください。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
法務局 登記申請手続のご案内(相続登記1/遺産分割協議編)
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
































