7月から妻が「月収11万円」のパートを開始! 今年の年収は「106万円」以内なので、パート先の社会保険の加入は“来年から”でも大丈夫でしょうか? 加入条件や注意点を解説
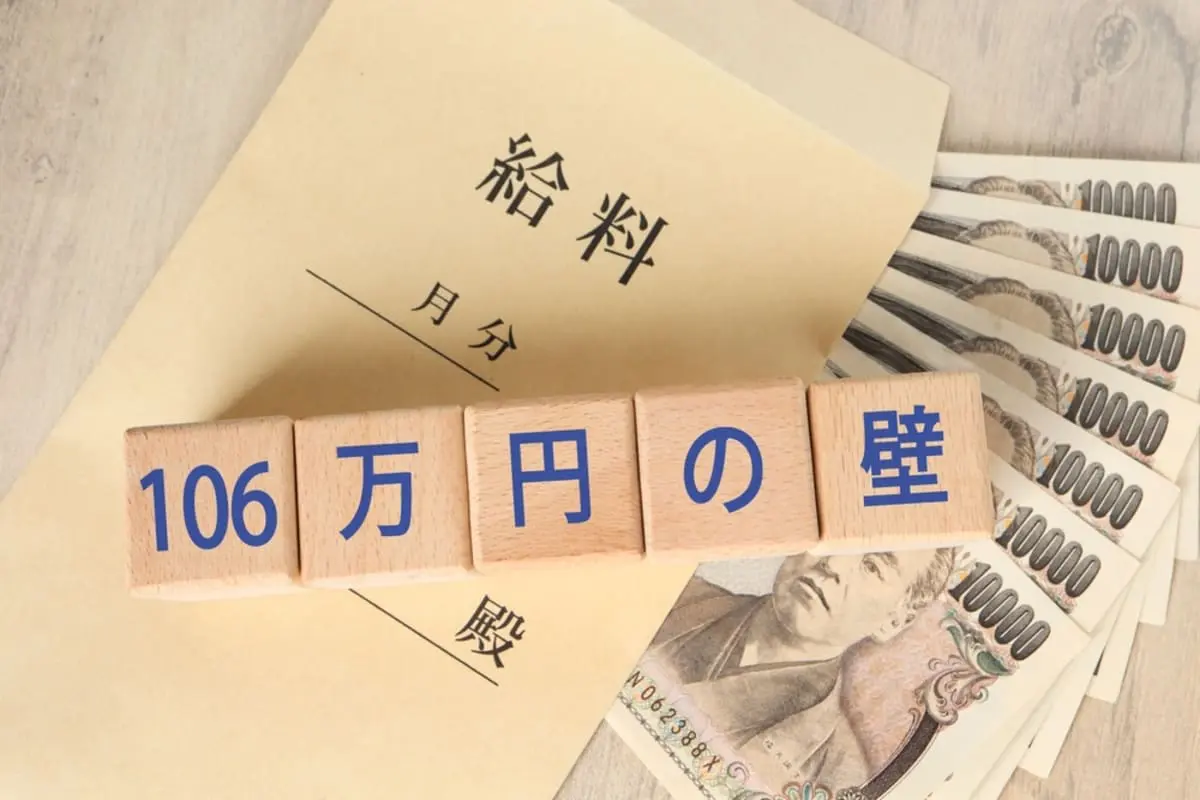
そうした中、「今年は途中から働き始めたから、社会保険の加入は来年からでいいのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。そこで本記事では、年の途中から働き始めた場合でも社会保険の加入が必要なのか、加入条件や注意点を解説します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
年収106万円を見込む場合は、年度途中でも社会保険の加入義務あり
パートやアルバイトでも、一定の条件を満たせば年度途中であっても社会保険への加入が必要になります。判断基準は「実際の年収」ではなく、1年働いた場合の見込み年収です。主な加入条件は以下のとおりです(※従業員51人以上の企業に勤務している場合)。
●週の所定労働時間が20時間以上
●月収8万8000円以上(年収換算で106万円以上)
●雇用期間が2ヶ月以上見込まれる
●学生でない
上記全てを満たすと、働き始めた月から社会保険の加入義務が発生します。また、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」では、次のように補足されています。
「契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします」
つまり、年収は見込みで判断されますが、週20時間以上の労働時間については実際の勤務実績が重視されます。
試用期間中の社会保険の加入はどうなる?
入社直後は、会社と労働者双方の適性を見極める「試用期間」が設けられることが一般的です。期間は1~6ヶ月程度で、契約内容も不安定になりがちです。このような試用期間中、社会保険の加入がどうなるのか疑問に思う人も多いでしょう。
日本年金機構によると、たとえ試用期間中であっても、以下のいずれかを満たす場合は「2ヶ月を超えて雇用される見込みあり」と判断され、入社日から社会保険の加入対象になります。
●雇用契約書などに「契約が更新される」または「更新される場合がある」と明示されている
●同じ事業所で、同様の雇用形態の従業員が、契約更新により2ヶ月を超えて働いている実績がある
一方、「雇用期間2ヶ月以内」とされており、更新の記載や実績もない場合は、その時点では加入対象外です。ただし、途中で契約内容が変更され、「2ヶ月を超えて雇用される見込みが出た日」からは、社会保険への加入義務が発生します。
社会保険に月途中で加入した場合、保険料はどのくらいかかる?
月の途中や月末に社会保険へ加入する場合、「保険料は日割りになるのか?」と疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、社会保険料は日割りではなく月単位で計算されるため、たとえ月末の1日だけの勤務でも、資格取得日がその月であれば1ヶ月分の保険料がかかります。
実際の保険料額は、加入する健康保険の種類(協会けんぽや組合健保など)や地域、標準報酬月額によって異なりますが、例えば月収11万円の場合、東京都で協会けんぽに加入すると、本人負担分は月およそ1万5000円となります(※2025年度時点)。
そのため、できるだけ無駄な負担を避けたい場合は、「月初(1日)」を入社日に設定するのが望ましいといえるでしょう。
まとめ
「年収106万円の壁」は、実際の年収ではなく、1年働いた場合の見込み年収で判断されます。そのため、条件に該当する場合は入社時から社会保険の加入義務が発生する点に注意が必要です。
本記事で解説した加入基準は現行制度に基づくものですが、早ければ2026年には年収要件の撤廃が予定されています。制度の見直しに備えて、今後の動向にも注目しておくとよいでしょう。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイトパート・アルバイトのみなさま
日本年金機構 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集
全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分から)の健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

































