年金を夫婦合わせて毎月「30万円」もらうには、現役時代の年収がいくらであるべき?
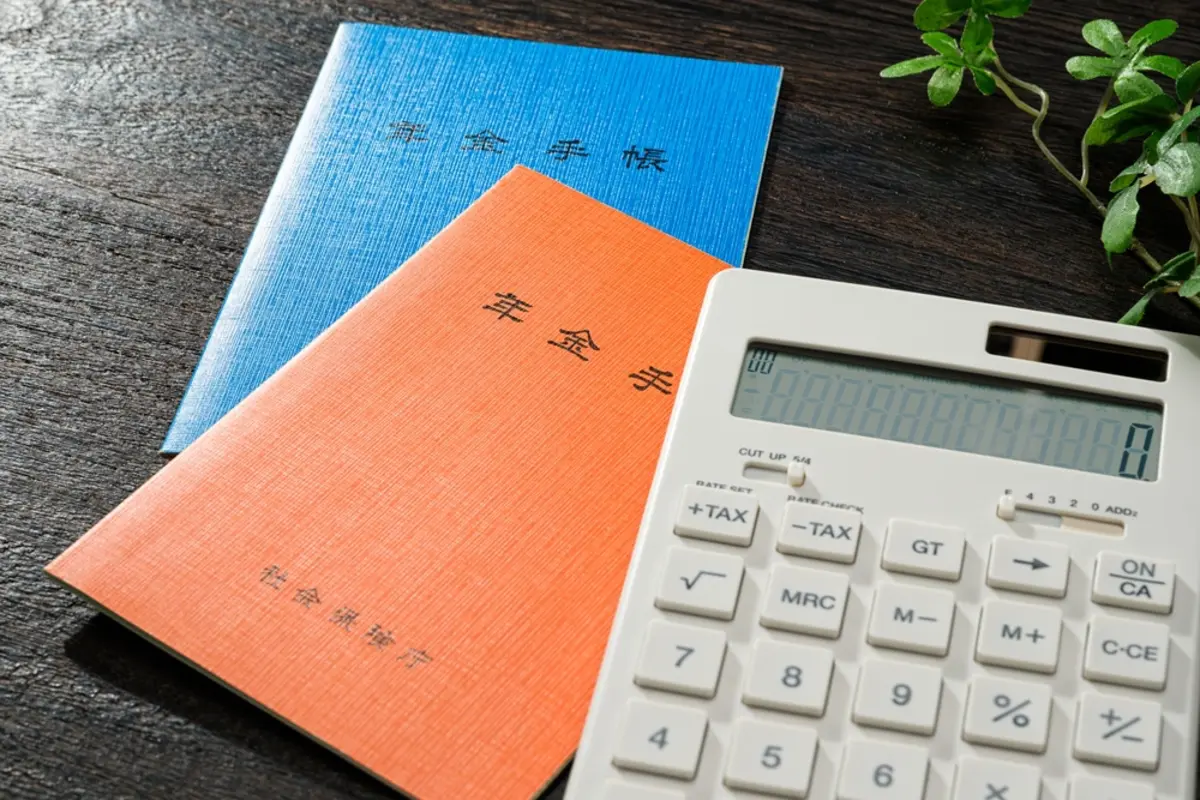
そこで、毎月夫婦で年金を30万円もらおうとしたら、実際に現役時代の年収がどれくらい必要になるのか試算してみました。

行政書士
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
年金を夫婦で毎月30万円得ることは簡単ではない
年金だけで、夫婦合わせて毎月30万円もの金額を得るのは、簡単ではありません。生計を支える夫と専業主婦の妻という世帯を例に、下記の条件で年金額を試算してみます。
・夫婦ともに1980年6月1日生まれ
・夫は20歳から22歳まで学生として国民年金に加入
・夫は23歳から65歳まで年収880万円で厚生年金に加入
・妻は20歳から22歳まで学生として国民年金に加入
・妻は23歳から59歳まで配偶者の扶養家族として国民年金に加入
・65歳0ヶ月で年金受給開始
・厚生労働省の公的年金シミュレーターで試算
すると、夫は年間283万円、月額換算で23万5000円ほどの年金を得ることができます。妻は年間80万円、6万6000円ほどの年金を得られます。
このように、妻が専業主婦や扶養内のパートである場合、年金で30万円の収入を得ようと思ったら、夫は23歳から65歳までの間、年収880万円の高収入で働きつづける必要があります。あまり現実的ではありませんが、年金だけで30万円の収入を得るというのはそれくらい難しいことのようです。
共働き世帯なら現実的になる
妻が専業主婦である場合に年金30万円の受給を実現するのは相当に困難ですが、夫婦共働き世帯であれば、月30万円の年金も現実的なものになります。いったん、下記の条件で試算してみます。
・夫婦ともに1980年6月1日生まれ
・夫は20歳から22歳まで学生として国民年金に加入
・夫は23歳から59歳まで年収690万円で厚生年金に加入
・妻は20歳から22歳まで学生として国民年金に加入
・妻は23歳から59歳まで年収400万円で厚生年金に加入
すると、夫の受け取る年金額は年間212万円となります。月額換算ではおよそ17万6000円です。対して妻の受け取る年金額は154万円となり、月額換算ではおよそ12万8000円となります。
夫婦合わせて、30万4000円程度の年金額になります。夫婦共働きであれば、月30万円という大きな額の年金の受給も、十分実現可能になりそうです。
老後月30万円の収入が必要ならば就労も検討すべき
老後に毎月の生活費として年金が30万円必要であるという場合、就労+年金収入で毎月30万円の収入を目指すというのも有効です。
年収400万円から600万円程度の夫と専業主婦の妻という世帯で、夫婦合わせて15万円から20万円程度の年金を受給するのであれば、比較的容易に実現することができそうです。
しかし、そこからさらに10万円から15万円程度上乗せして30万円とするには、現役時代にかなりの高収入を得ていたり、夫婦共働きであったりする必要が出てきます。そこで、毎月30万円の収入を現実的なものとするためには、就労が有効と考えられます。
例えば、先にみたように年収690万円で働いていた夫が、その後60歳から70歳まで年収400万円で働いた場合、65歳から受け取る年金は年間232万円となります。老後に働かない場合に比べて、月額換算で19万円と、1万3000円ほど月々の年金額が増加します。
また、70歳から受け取る年金額は年間252万円となります。月額換算では21万円程度です。就労による毎月の給与と年金の増加額を含むと、老後月30万円の収入確保も随分現実的になってきます。
まとめ
年金だけで夫婦合わせて毎月30万円を受け取ろうと思うと、高収入であったり、共働きで一定以上の世帯年収が必要となったりするなど、そう簡単ではありません。どうしても老後に月30万円の収入が必要であれば、年金だけでなく、就労と合わせて毎月30万円の収入を得られるよう考える方が現実的です。
老後の生活については、年金だけで全て生活を賄おうとするのではなく、必要に応じて就労することや、不足する部分を貯蓄など資産の切り崩しで対応できるよう計画を立てて準備しておくことが大切でしょう。
執筆者:柘植輝
行政書士


































