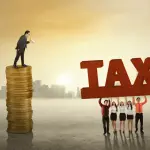国民年金の「底上げ」が議論されているって本当?今後の「年金受給」はどう変わる?

そこで本記事では、国民年金の底上げが議論されている背景や、今後見直しが進められる制度について調べてみました。今後の年金受給は老後生活で重要なポイントとなりますから、参考にしてください。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
国民年金の底上げが議論されている背景
日本の公的年金制度は2階建てといわれていて、国民年金をベースに、会社員であれば厚生年金も受給できます。年金制度を維持していくには、財源の確保が必要不可欠ですが、人口や経済の動向に大きな影響を受けるため、年金財政の健全性を検証する必要があります。
厚生労働省「令和6(2024)年財政検証結果の概要」によると、2024年に実施された財政検証では、国民年金の給付水準が現在36.2%であるのに対し、過去30年間と同じ程度の経済状況が続くと、2057年度では25.5%にまで低下することが予想されました。
国民年金の底上げを実現するための案として出されているのは、マクロ経済スライドの短縮です。これは2004年の年金制度改正において導入された制度で、給付水準を物価や賃金の上昇よりも低くおさえて、年金制度の支え手となる現役世代の負担が重くなりすぎないようにする仕組みです。
厚生年金については、働く高齢者や女性の増加にともない財政が改善し、マクロ経済スライドは2026年度に終了すると予想されています。しかし国民年金については、財政状況がよくないため、2057年まで続くとされています。
この抑制措置の長期化が、将来の給付水準の低下につながるため、マクロ経済スライドの短縮によって国民年金の底上げを実現させる議論が行われました。
なお、国民年金の給付を増やすための財源は、厚生年金保険料の積立金および国庫負担で賄うとしていて、今後も財源確保の課題は続くと考えられます。
今後見直しが進められる制度
第21回 社会保障審議会年金部会では、マクロ経済スライドの短縮のほかにも、在職老齢年金制度や標準報酬月額の上限についても話し合われました。
これらの制度は今後見直しが進められることになっていますが、年金受給にも大きな影響を与えるものです。各制度の概要や見直しのポイントは、以下の通りです。
在職老齢年金制度
在職老齢年金は、定年後も働いて一定以上の収入を得た場合に厚生年金の一部または全額が支給停止となる制度です。現状では、年金と賃金を合わせて50万円を超えると、年金額は徐々に支給停止になり、合わせて70万円になると全額停止になります。
この制度が、高齢者の働き方に影響を与えていることが指摘されました。年金の賃金の合計額を、現在の基準値である50万円の手前の48万円あたりで調整している人が増えているようです。
人手不足が課題となっているなか、高齢者の働く意欲を失わせる制度であるとされ、年金が減らされる基準を50万円から62万円または71万円に引き上げるか、制度そのものを廃止するかが見直しの方向性となっています。
厚生年金の標準報酬月額
厚生年金の保険料は標準報酬月額を基に算定され、収入が多い人は保険料が高くなります。しかし平均的な給与の2倍程度を目安に上限が定められていて、現在の上限は65万円です。収入のある加入者にはより多くの保険料を負担してもらうため、上限の引き上げが案として挙げられています。
厚生年金の標準報酬月額の上限65万円に該当する人は、全体で6.5%いるとのことです。男性だけで見ると、上限65万円に該当する人が一番多く、9.2%を占めています。
賃上げが続くと上限65万円の該当者はさらに増える見通しであることを踏まえて、上限を75万円・79万円・83万円・98万円のいずれかに引き上げる案が示されました。これにより、保険料収入は年間で4300億〜9700億円の増加につながると予想されます。
今後の年金受給は老後生活で重要なポイント!年金改革案に注視しつつ備えておくことが大切
国民年金の給付水準低下が予想されるなか、国民年金の底上げが議論されていることは注目に値します。物価上昇が続く昨今、今後の国民年金の受給額が増えると家計は助かるでしょう。
第21回 社会保障審議会年金部会では、国民年金の底上げを実現するための案としてマクロ経済スライドの短縮が挙げられました。また在職老齢年金制度や厚生年金の標準報酬月額の見直しが議論されました。
今後の年金受給は老後生活で重要なポイントですから、年金改正案に注視しつつ、老後の働き方や生活スタイルについて考えておくことも大切です。
出典
厚生労働省 第21回 社会保障審議会年金部会(議事録)
厚生労働省 令和6(2024)年 財政検証結果の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー