年金のお知らせを見ると、私は「第3号」でした。第1号・第2号・第3号で受け取れる年金額に差が出るのは本当でしょうか?
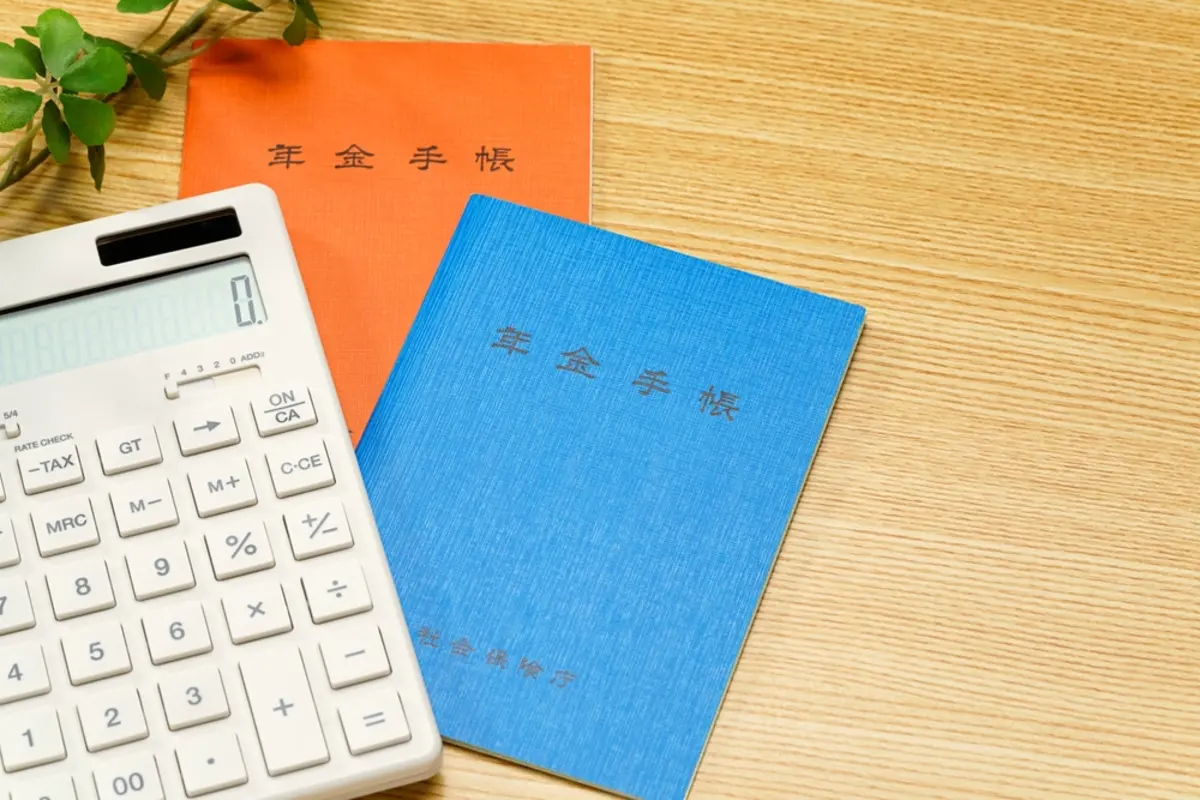
今回は、国民年金の被保険者区分について解説するとともに、各被保険者が受け取ることができる年金額について解説します。

ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/
年金制度の種類と被保険者区分
1. 年金制度の種類
日本の公的年金制度は、国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての方が加入する国民年金と、会社員などの方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています(※1)。
2. 国民年金の被保険者区分
全国民が対象となる国民年金の被保険者は、第1号、第2号、第3号の3つに区分されています(※1)。
第1号被保険者:農業・自営業・学生・無職の方など
第2号被保険者:会社員・公務員の方など
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
被保険者区分と年金制度
1. 加入する年金制度
自営業者などの第1号被保険者は、国民年金のみに加入しています。会社員などの第2号被保険者の方は、国民年金と厚生年金の両方に加入しています。第3号被保険者は、国民年金のみに加入しています。
図表1 《加入する年金制度》
| 年金制度 | 国民年金 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 加入 | |
| 第2号被保険者 | 加入 | 加入 |
| 第3号被保険者 | 加入 |
(※1を基に筆者作成)
2. 支払う保険料
第1号被保険者は、20歳から60歳になるまで定額の国民年金保険料を支払います。第2号被保険者は、報酬に比例して算定される厚生年金保険料を事業者と折半して支払います。第3号被保険者は、保険料を支払う必要はありません。
図表2 《支払う保険料》
| 年金制度 | 国民年金 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 支払い | |
| 第2号被保険者 | 支払い | |
| 第3号被保険者 |
(※1を基に筆者作成)
第2号被保険者および第3号被保険者は、その被保険者である期間は、国民年金保険料を支払った期間として認められます。
なお、厚生年金保険料として徴収された保険料は、基礎年金の支払いに必要な財源として振り分けられています(※2)。
3. 支給される年金
20歳から60歳になるまでの40年間(480月)で第1号被保険者として保険料を納付した月数と、第2号被保険者または第3号被保険者であった期間の月数が合わせて480月ある場合は、国民年金から満額の老齢基礎年金が支払われます。
加えて、第2号被保険者には、加入期間と平均報酬に応じた老齢厚生年金が合わせて支給されます。
したがって、20歳から60歳になるまで全期間第1号被保険者であって、国民年金保険料を全期間支払った方には、満額の老齢基礎年金が支払われます。
20歳から60歳になるまで全期間第2号被保険者であった方には、満額の老齢基礎年金と、加入期間と平均報酬に応じた老齢厚生年金が支払われます。
20歳から60歳になるまで全期間第3号被保険者であった方、またはその一部が第1号被保険者であってその期間の国民年金保険料を全て支払った方には、満額の老齢基礎年金が支払われます。
図表3 《支給される老齢年金》
| 年金制度 | 国民年金 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 支給 | |
| 第2号被保険者 | 支給 | 支給 |
| 第3号被保険者 | 支給 |
(※1を基に筆者作成)
なお、20歳から60歳までの期間中に第1号被保険者として保険料を支払わない期間があった場合は、その月数分、老齢基礎年金が減額されます。
また、厚生年金の被保険者期間がある第1号被保険者や第3号被保険者には、老齢基礎年金に加えて、加入期間と平均報酬に応じた老齢厚生年金が合わせて支給されます。
まとめ
国民年金には、自営業などの第1号被保険者、会社員などの第2号被保険者、第2号被保険者の被扶養配偶者の第3号被保険者があります。
第3号被保険者は、第1号被保険者と同様に老齢基礎年金は支給されますが、第2号被保険者に支給される老齢厚生年金は支給されないため、第2号被保険者に比して年金額は少なくなります。
出典
(※1)日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
(※2)厚生労働省 [年金制度の仕組みと考え方] 第2 公的年金制度の財政方式
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

































