毎月「約4万円」の厚生年金保険料を払っています。将来何歳まで受け取れば、払った保険料“以上”の年金がもらえますか?
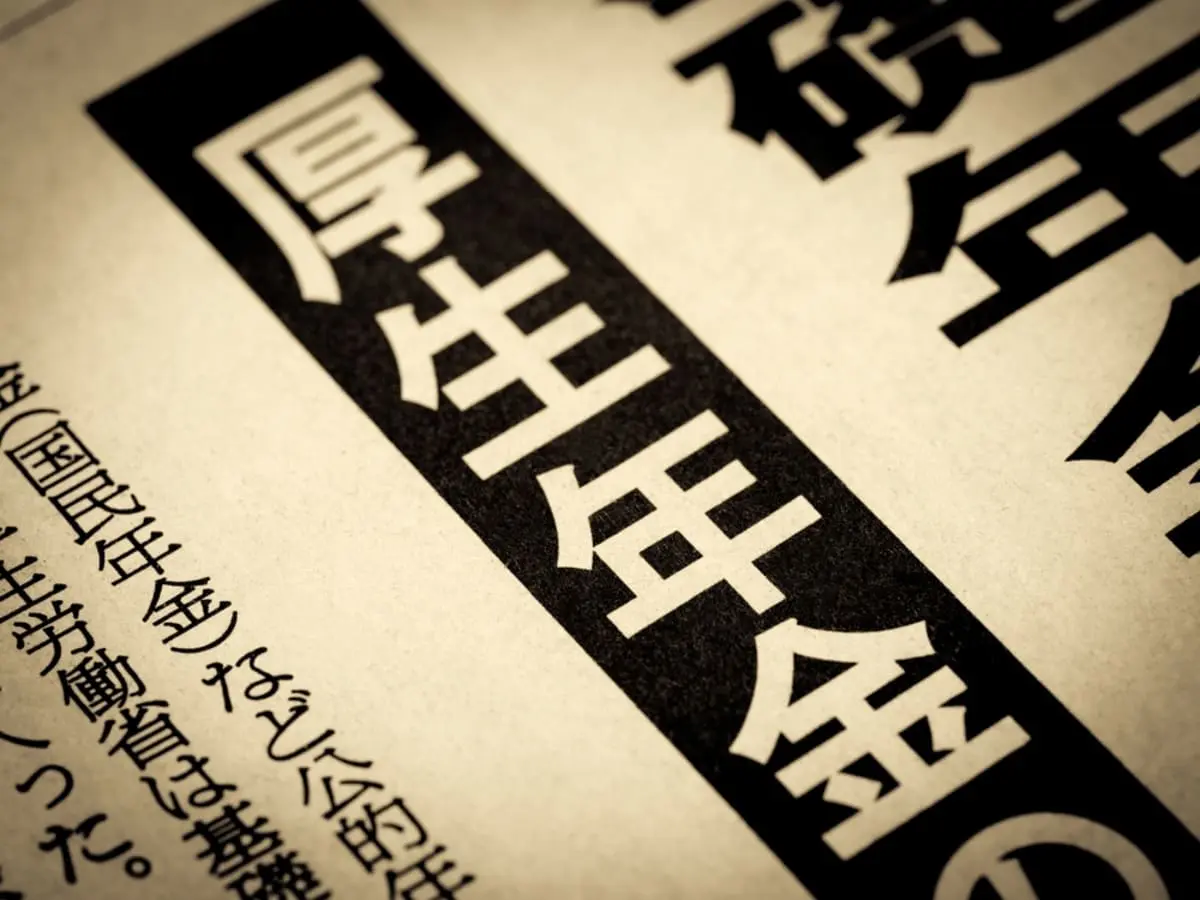
一方の厚生年金は、会社に勤務している人が支払うもので、給料に対して納付額が決定します。国民年金と厚生年金の両方に加入している人は、定年後に2種類の年金を受給できます。
しかし、老後にどのくらいの年金がもらえるかは気になるところです。今回の記事では、毎月4万円の厚生年金を支払っている場合、何歳になれば払った金額以上を受け取れるかを解説します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
厚生年金の支払金額はどう決まる?
厚生年金では、会社の給料と加入期間に応じた標準報酬月額が設定されます。個人の標準報酬月額に厚生年金保険料の18.3%を掛けた金額が支払額です。しかし、厚生年金の支払いは会社と折半しており、個人がすべての金額を負担しているわけではありません。
ここからは、毎月の給料が20万円の人を例に見てみましょう。厚生年金保険料額表によると、給料が毎月20万円の人は標準報酬月額が20万円です。したがって、個人が払う厚生年金の保険料は、20万円×9.15%(会社との折半のため)=1万8300円です。
なお、賞与に対しても保険料がかかります。例えば、賞与が50万円だった場合の標準報酬月額は50万円で、上記の計算式に当てはめると、50万円×9.15%=4万5750円となります。4万円の厚生年金保険料を支払っている場合の標準報酬月額は44万円です。
厚生年金はいくらもらえる?
令和6年度より、年金受給額が1.9%引き上げとなりました。令和7年度の厚生年金の平均月額は23万2784円です。ここからは、毎月4万円保険料を支払った場合、厚生年金がどのくらいもらえるか見ていきます。厚生年金の計算は、以下のように加入時期によって異なります。
・平成15年3月以前の加入:平均標準報酬月額×7.5÷1000×平成15年3月以前の加入月数
・平成15年4月以降の加入:平均標準報酬額×5.769÷1000×平成15年4月以降の加入月数
平成15年4月以降から30年間加入しており、平均標準報酬額が44万円の場合、上記の計算式に当てはめると、44万円×5.769÷1000×360ヶ月=約91万3800円と、厚生年金の1年間の受取額を計算できます。月額にすると、約7万6000円です。
何歳まで受け取れば元が取れる?
何歳まで年金を受け取れば、支払い額以上の金額がもらえるのでしょうか。
厚生年金4万円を30年間支払うと合計で1440万円です。上記の例では、1440万円以上の年金を受け取るには、1440万円÷91万3800円=約16年かかる計算です。年金の受給開始は65歳からなので、81歳になれば支払った保険料以上の年金を受け取れることになります。
厚生年金の元は取れる
厚生年金4万円を30年間払い続けた場合、65歳から受取を開始すれば81歳で元が取れることが分かりました。厚生年金は会社と折半での支払いになるため、すべてを自己負担するわけではありません。
ただし、給料によって納付額が異なるため、将来もらえる年金額は個人によって異なります。老後の年金額を知るためには、自分がいくら払っているのかを確認しておくことが大切です。
納めた年金額を知っておけば、自分が何歳になったら元が取れるのかを計算できます。なお、厚生年金は毎月の給与と賞与に対してもかかることに注意しましょう。
また、令和6年度から年金の受給額が引き上げられました。厚生年金を払っている人は国民年金も受給できるようになったため、老後の生活が安定するでしょう。老後の生活のために、年金はきちんと納めることが大切です。国民の義務であることを忘れずに、必ず納めるようにしましょう。
出典
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー


































