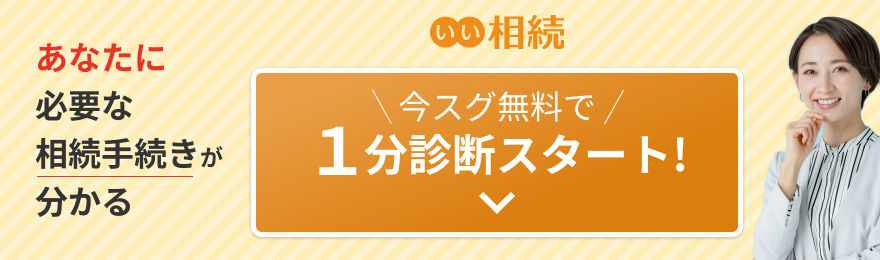遺留分とは?遺留分侵害額請求や計算方法についてもわかりやすく解説

但し、相続人のメンバーや人数や法的な保証取り分(遺留分)を侵害した状況によっても、請求できる対象者や請求額が変わるため注意が必要です。
この記事では、相続や遺留分の基本ルールおよび遺留分侵害額請求の請求対象や方法についてや、制度の分かりづらい部分も解説していきます。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
目次
遺産の遺留分とは? 権利をもつ相続人とは?
遺留分とは、被相続人(死亡した方、財産の所有者)の法定相続人に保証される最低限の遺産取得分です。
そのため、たとえ遺言によって別の者へ多額の遺産を相続するよう遺言で被相続人が生前に指示をしていたとしても、遺留分の権利をもつ相続人は「遺留分にあたる相続財産を返してほしい」と主張して手続きをすれば、一定割合の財産が取得できるのです。
遺留分をもつ相続人
下記の者は、被相続人の遺産を必ず相続できる遺留分をもっています。
・子どもや孫(直系卑属)
・妻や夫(配偶者)
・両親や祖父母(直系尊属)
この立場にある方の遺留分が自動的に消えることはありません。なお、遺留分の請求権者に兄弟姉妹は含まれません。
遺留分をもたない相続人
下記の3つに該当する場合には、相続人に遺留分が認められません。なお、はじめから遺留分がない場合と後天的に剥奪される場合があります。
(1)兄弟・姉妹や甥(おい)・姪(めい)
被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなった場合の相続人候補である甥姪には、はじめから遺留分は認められません。
(2)欠格事由があったために除外された元相続人
欠格事由とは、下記に該当する場合です(民法第891条)。
・故意に自分よりも相続権が優先する者を殺害もしくは加害した場合
・上記の殺害や加害を知っていたのに罪を追及せず黙っていた場合
・詐欺や脅迫によって被相続人の遺言内容を変えさせようとした場合
・遺言書を偽造(コピー)・変造(書き換え)・破棄・隠匿(隠す)した場合
つまり、通常なら遺留分の権利をもつ相続人であっても、相続人から除外された場合には遺留分の権利も併せて剥奪されるというわけです。
(3)相続人の廃除によって相続人から除外された元相続人
相続人の廃除とは、被相続人を虐待したり重大な侮辱を加えたりした者は相続権を剥奪されるというルールです(民法第892条)。この場合も、相続人ではなくなったため遺留分も同時に失います。
遺留分はあらかじめ放棄できる
遺言によって遺留分が誰かに侵害されていても、それを取り戻すアクションを起こさなければ遺言による相続財産の分配を認めたことになり、相続は遺言書どおりの割合で実行されます。遺留分はあくまでも権利であって、権利を主張して遺産を取り戻すかどうかは権利者の自由なのです。
なお、遺留分は相続発生前(被相続人がまだ生きているうち)にでも放棄できますが(民法1043条)、遺留分の生前放棄は意思表示のみの場合や念書に遺留分を放棄すると書いただけでは認められません。放棄する相続人が家庭裁判所へ申し立てる一定の手続きが必要であり、一旦遺留分を放棄すれば放棄の意思表示を撤回するのは困難です。
遺留分の侵害があると相続人間の揉めごとに繋がりやすいため、遺産を特定の方へ集中させる際には、被相続人は遺留分の割合に配慮が必要でしょう。
遺産に対する遺留分の割合と計算方法
遺留分とは、法定相続分のおおむね半分の割合の取得が保証された法律の規定で、相続人のメンバーや人数によって割合が変動します。
遺留分は法定相続分の半分
遺留分は、権利者に最低限保証された遺産の取得割合です。
遺留分の割合は「法定相続分の2分の1」であり、相続人が直系尊属のみの場合は「法定相続分の3分の1」になります。なお、法定相続分とは法律で定められた遺産分割の分配割合です。相続人のメンバーと遺留分の割合との関係は後ほど解説します。
遺留分の割合の計算は2ステップで行う
遺留分の割合は、下記の2つのステップに分けて計算します。
(1)全体の遺留分割合(最大の割合)を計算する
(2)相続人に応じた遺留分割合を個別に計算する
それぞれの場合について以下で解説します。
全体の遺留分割合(最大の割合)を計算する
まずは全体の遺留分割合がどれくらいあるのかを計算しますが、遺留分割合は相続人のメンバーによって以下の図表1のようになります。
図表1
| 相続人メンバー | 全体の 遺留分割合 |
各相続人の遺留分割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
| ・配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | – | – | – |
| ・配偶者 ・子ども |
2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | – | – |
| ・配偶者 ・父母 |
2分の1 | 3分の1 | – | 6分の1 | – |
| ・配偶者 ・兄弟姉妹 |
2分の1 | 2分の1 | – | – | なし |
| ・子どものみ | 2分の1 | – | 2分の1 | – | – |
| ・親のみ | 3分の1 | – | – | 3分の1 | – |
| ・兄弟姉妹のみ | なし | – | – | – | なし |
法務局 法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)を基に作成
親などの直系尊属のみが相続人の場合
親や祖父母などの「直系尊属のみ」が相続人なら、全体の遺留分割合は遺産全体の3分の1です。
それ以外の場合
「直系尊属のみ」以外なら、全体の遺留分の割合は遺産全体の2分の1です。
各相続人の遺留分割合を計算する
全体の遺留分の割合が出れば、その割合に各相続人の「法定相続分」を合わせて各相続人の遺留分の割合を計算します。なお、相続人メンバーごとの遺留分の割合は前出の図表1をご覧ください。
遺留分の具体的な計算例
前提条件:遺産総額4000万円、相続人は配偶者と子ども2人
遺留分の割合
・配偶者:4分の1
・子ども:8分の1ずつ
遺留分に基づく金額の計算
配偶者:4000万円×1/4=1000万円
子ども:4000万円×1/8=500万円ずつ
相続財産が不動産の場合の遺留分の計算
相続財産に不動産が含まれる場合には「不動産の相続開始時点における価格」を算定の基準にします。この場合の不動産価格の評価方法は、土地なら「公示地価」「相続税路線価」、土地や建物なら「不動産鑑定評価額」「固定資産税課税評価額」など、以下の図表2のような評価額を参考にして計算します。
図表2
| 不動産評価額 | 評価額の概要 |
|---|---|
| 公示地価 | ・国土交通省が毎年3月下旬に発表している、標準地の正常な価格。 ・流通価格に(時価)に近い金額。 |
| 相続税路線価 | ・国税庁が毎年7月1日に発表している、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額。 ・公示地価の約80%に設定されている。 |
| 不動産鑑定評価 | ・不動産経済価値を判定し、その結果を価額にしたもの。 ・不動産鑑定士が「原価法、取引事例比較法、収益還元法」を基準に評価している。 |
| 固定資産税課税評価額 | ・土地や家屋などの固定資産にかかる固定資産税を決める際に基準となる評価額のこと。 |
筆者作成
遺留分を金銭で取り戻す「遺留分侵害額請求」
遺留分侵害額請求は、権利者がルールにしたがって対象者へ請求をかけて遺留分に相当する金銭を取り戻します。但し、請求によって金銭を受け取ると相続した財産が後日増えるということになるため、それに伴って相続税の納税額も増えるという点にご注意ください。
遺留分への侵害は「遺留分侵害額請求」で対抗する
遺留分を侵害された場合には、遺留分の割合を超過する遺産を取得しようとする相手に対して「遺留分侵害額請求」を申し立てます。
遺留分侵害額請求とは、「遺留分を超過している遺産を金額に換算して、お金で返してもらう手続き」です。例えば、遺言書にて全ての遺産を配偶者へ渡すとしている場合に、子が侵害された遺留分が1000万円分と換算できたなら、子は配偶者に「1000万円(お金)」を請求できるのです。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求との違い
遺留分の請求方法は2019年(令和1年)7月1日の相続法の改正により変更されましたが、以前は侵害された遺留分への請求方法は「遺留分減殺請求」というものでした。この遺留分減殺請求による方法は「お金」ではなく「遺産そのもの」の返還を受ける手続きでした。
株式や車両など数によって分けられる遺産なら問題ありませんが、分割が難しい不動産では遺留分の割合に相当する範囲の不動産を共有するしかありません。しかし、共有不動産では、売却だけでなくリフォームや賃貸や担保設定などを行う場合に共有者の過半数〜全員の同意を要するなど、自由な運用を阻害するルールがあります。
しかも、共有不動産を分割するには「共有物分割」という裁判所の手続きを経なければならないなど、相続人間の揉めごとの火種になることが多かったのです。
そこで、遺留分の返還は原則として「お金で取り戻す」という方法に変わり、現在のように1回で解決できて運用しやすい手続きになったのです。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
遺留分侵害額請求までの流れ
遺留分の侵害に気づいた場合には、状況に合わせた以下の順番と方法で遺留分侵害額請求を実行していきます。
遺留分を要求する直接の話し合い
通常の遺留分侵害額請求は、まず遺留分を侵害している相手と遺産の配分割合について話し合うところからはじめます。相手とスムーズに話しがまとまるなら簡単なのですが、気心知れた身内であっても後日のトラブルを想定して、事前に内容証明郵便など確実な証拠になる文書の形式で請求書を送るなどの検討をしましょう。
この方法で相続人間の合意が整ったら「遺留分侵害額の合意書」を取り交わして、合意内容にしたがって金銭の支払いを受けます。
家庭裁判所が介入する調停
直接の話し合いでは合意しそうにない場合は、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」の申し立てを行います。この手続きを行う管轄裁判所は、原則として相手が居住する住所地を管轄する家庭裁判所になります。なお、調停では家庭裁判所から調停委員が派遣され、利害が対立する両者を合意へと調整していきます。
例えば「被相続人の最後の意思である遺言を100%尊重すべきだ!」という遺留分を侵害する相手方に対して、調停委員は「遺留分は法的に保護された権利なので払うしかない」と説得してくれます。そして、遺留分侵害額の金額や支払い方法についての合意が成立すれば、申立人へとお金が支払われます。
調停から遺留分侵害額請求訴訟へと移行
調停委員の努力もむなしく合意に至らない場合は、調停から「遺留分侵害額請求訴訟」へと移行します。裁判所は、対象の遺産を鑑定評価して遺留分に従い授受すべき金額を計算し、相手へ支払い命令を下します。この訴訟手続きは、双方の意向を汲み取って話し合うのではなく、裁判官から金銭の支払い命令が下されるため、当事者が反対することはできず結果に対する合意も不要です。
遺留分侵害額請求権の消滅時効と時効停止の方法
遺留分侵害額請求権には期限があり、比較的短いです。ただし、消滅時効の進行を止めて請求権を保留しておきたい場合には、消滅時効を停止させる手続きがあります。
遺留分侵害額請求の消滅時効期間および除斥期間
遺留分侵害額請求権の消滅時効は「相続開始および遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内に遺留分を請求する」という要件があります。つまり、遺留分侵害の事実を知ってから何も行動しないで1年間放置した場合には、以後遺留分の請求権を失います。
また、相続も遺留分の侵害も全てを知らなかった場合でも、相続が開始した時点から10年が経過してしまうと遺留分の請求権を失ってしまうのでご注意ください。
遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
遺留分侵害額請求権の消滅時効は、相続開始および遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に「請求」すれば、消滅時効の進行がいったん止まります。
請求は、消滅時効の進行を止める重要なものですが、その請求方法に関する規定はないため、書面でなくても構いません。しかし、口頭や簡易な請求書による請求では、相手方が「遺留分侵害額の請求は受けていない」と言い張る可能性があります。
それを阻止するためにも請求は、「内容証明郵便」を使うことがよいでしょう。公証役場に請求書面が証拠として保管され、相手方が請求書面を受け取ったことが記録されるので安心です。
その他に遺留分が侵害されるケース
遺留分は、遺言による偏った持分の相続や明白な生前贈与などではなく、少しずつ累積して遺留分を侵害したり、相続によって請求する遺留分が増える場合があります。
生前贈与の累積で遺留分を超過した場合
自分の財産を誰かに渡すことを「贈与」といい、贈与者(財産を渡す人)が生存中に受贈者(財産を受け取る人)へ財産を渡す行為を「生前贈与」といいます。生前贈与は、被相続人が生前に行う贈与契約で、贈与者と受贈者とが契約書を使用せずに口頭で意思確認をしただけで成立する諾成契約(法律行為)です。
生前贈与された財産に対して遺留分請求を行う際に、対象となる財産は原則として「相続開始前の1年間」に渡されたものだけに限ります。但し、贈与者(被相続人)と受贈者(贈与を受け遺留分を侵害した人)の双方が「生前贈与によって遺留分を侵害する」と知りながら生前贈与を行った場合には、相続開始から1年以上前の生前贈与であっても遺留分請求の対象範囲に含まれます。
なお、法定相続人への生前贈与が「特別受益」に該当する場合には、相続開始前10年以内の贈与が遺留分請求の対象になります。ちなみに、特別受益とは法定相続人の一人が特別に得ていた利益のことで、下記のような財産の授受も特別受益と見なされます。
・生活費の援助
・不動産や車の贈与
・マイホーム購入の頭金
・進学費用の援助
・起業資金の援助
・家賃の免除
・結婚その他のお祝い金
一方で、遺留分侵害額請求の対象とならない下記の例外もあるため、併せてご確認ください。
・被相続人が代表をつとめた中小企業の株式および事業用財産を後継者に対して贈与する場合
・個人事業主として所有していた事業用財産を後継者に対して贈与する場合
以上は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の「遺留分に関する民法の特例」(第4条)で規定されている遺留分侵害額請求の対象外になります。ただし、この取り扱いにするには、生前に規定にある一定の手続きを完了しておかなければなりません。
死因贈与で遺留分を超過した場合
「死因贈与」とは、贈与者と受贈者が死亡をきっかけとする贈与に関して生前に合意すれば契約が成立し、贈与者が死亡した瞬間に財産移転の効力が生じるという法律行為です(民法第554条)。
死因贈与は、死亡をきっかけに贈与の効力を発動する契約であり、多額の財産が死因贈与によって移転したことで法定相続人の遺留分が侵害されたなら、遺留分の割合に超過する財産分の金銭を請求できます。
二次相続の相続人が遺留分侵害額請求権者になる
遺留分の権利者が、遺留分侵害額請求権の消滅時効前に死亡した場合、その請求権は二次相続によって遺留分権利者の相続人へと承継されます。
したがって、一次相続時点で遺留分侵害額請求がなされなかった場合でも、二次相続になって忘れた頃に一次相続時の遺留分侵害額請求が実行される可能性があるのです。つまり、当時遺留分を侵害された本人が亡くなったとしても、請求権が消滅するわけではありません。
また、一般的に二次相続では一次相続よりも相続人(遺留分権利者)の人数が減ることが多いため、各相続人の遺留分割合は逆に増えることが多くなります。
一次相続:母親(遺留分4分の1)・息子(遺留分4分の1)
↓
二次相続:息子(遺留分4分の2)
遺留分侵害額請求をかける順序
遺留分侵害額請求の対象になる財産移転は「遺言」「死因贈与」「生前贈与」の主に3種類を原因として起こります。もしも、被相続人が遺言と死因贈与と生前贈与の全てを行っていた場合に、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行う正しい順番は法律で規定されています。(民法第1047条)
(1)遺言による移転財産が贈与によるものより優先する
対象になる財産移転が遺言と贈与によるものであるなら、まずは遺言によって移転した財産に対して遺留分侵害額請求をかけます。
(2)遺言の次は死因贈与の移転財産に対して請求
遺言による移転財産への遺留分侵害額請求でも侵害分に満たない場合には、贈与を受けた者へ請求することになります。このとき、贈与が複数あるような場合には贈与日付が新しい贈与から請求をかけることになります。
新しい贈与であれば、死因贈与が生前贈与よりも直近の新しい贈与になります。
(3)死因贈与の次は日付の新しい生前贈与に請求
死因贈与の次は生前贈与が対象になります。このとき、生前贈与が時期をずらしていくつか行われている場合には、日付が新しい贈与から順に請求します。
(4)複数の生前贈与は贈与額の割合で振り分けて請求
同時に生前贈与を受けた受益者が複数人いる場合には、贈与額の割合に応じて遺留分の請求を行います。
遺留分侵害額請求で侵害額に相当する金銭を取り戻す
遺留分とは、法定相続分の約半分の割合の相続財産の取得を法律で保証する割合のことで、その割合が侵害された場合には、遺留分侵害額請求によって侵害額に相当する金銭を取り戻すことができます。
遺留分は、遺言や生前贈与など明白な侵害もあれば、知らないうちに累積して侵害されていることもあります。この遺留分侵害額請求権の消滅時効は1年と短い期間であり、請求は裁判所を介した手続きが必要になるうえに、身内同士が揉めているケースも少なくありません。
そのため、相続の割合への疑問や遺留分野侵害に対する請求手続きはご自身で判断して行うのではなく、弁護士などの法律のスペシャリストに相談するとよいでしょう。
出典
法務局 法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)
e-Govポータル 民法
国土交通省 地価・不動産鑑定 地価公示
国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
e-Govポータル 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通省 不動産鑑定評価基準
e-Govポータル 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー