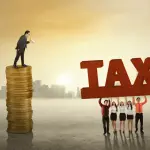iDeCo+(イデコプラス)ってなに? どんなときに対象になるの?

この記事では、iDeCo+の要件や内容についてお伝えします。

FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士
保険代理店勤務を経て独立。高齢出産夫婦が2人目を産み、マイホームを購入しても子どもが健全な環境で育ち、人生が黒字になるようライフプラン設計を行っている。子どもが寝てからでも相談できるよう、夜も相談業務を行っている。著書に「書けばわかる!わが家の家計にピッタリな子育て&教育費のかけ方」(翔泳社)
iDeCo+を導入できる企業とは
iDeCo+(イデコプラス)とは愛称で、「中小事業主掛金納付制度」といいます。iDeCo+を導入するには大きく2つの要件があります。
1つ目は、従業員数が300人以下であることです。ここでいう従業員とは、民間企業に勤める厚生年金被保険者をいいます。したがって、厚生年金に加入していない人は従業員としてカウントしません。
また、事業所が複数ある場合は、全事業所の従業員を合計して300人以下である必要があります。
2つ目の要件は、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金を実施していないことです。以上の2つの要件をクリアすればiDeCo+を導入できます。
対象者となる従業員
iDeCo+は、従業員のiDeCoの掛け金に会社が上乗せをする制度ですから、大前提として従業員がiDeCoをしていないと上乗せできません。言い方を変えると、iDeCoをしている従業員(厚生年金被保険者)であれば、誰でも対象になります。
ただし、掛け金を上乗せする対象者に条件をつけることは可能です。例えば、勤続3年以上など一定の勤続期間以上の従業員のみを対象としたり、営業職の従業員のみなど一定の職種だけを対象としたりすることができます。
条件に合えば役員でも対象になりますが、一方でiDeCoをしていない従業員は対象ではありません。これら従業員に対して、iDeCoの加入を強制したり、会社の掛け金だけを拠出したりすることもできません。
掛け金の設定
掛け金は、加入者掛け金と会社の掛け金の合計が5000円以上2万3000円以下の範囲で、加入者と会社が1000円単位で決められます。
加入者掛け金をゼロにすることはできないので、加入者は最低1000円の拠出が必要です。会社の掛け金は、事務手続きを考えると全員同額が最も簡便ですが、職種や勤続期間ごとに変えることも可能です。
また、年に1回掛け金の金額を変更することが可能ですが、変更後に加入者と会社の掛け金合計が2万3000円を超えてしまうと、加入者掛け金は自動的に引き下げられ、5000円未満だと掛け金の引き落としが停止されます。
納付方法
iDeCo+では、加入者の掛け金を給与天引きし、会社の掛け金を上乗せして会社が国民年金基金連合会に納付します。iDeCoの掛け金は全額所得控除可能ですが、控除処理は会社が行うため、従業員が手続きを行う必要はありません。会社は毎月給与で源泉処理を行います。
導入手続き
iDeCo+を実施するには労使合意が必要です。iDeCo+の制度説明やiDeCoに加入していない従業員に会社は掛け金を拠出できないこと等に同意を得ます。届出書類はiDeCo公式サイト(※)に記載されていますので参考にしてください。
不備がない場合でも、書類提出から初回引き落としまで2ヶ月ほどかかります。余裕を持ってスケジュールを組みましょう。制度開始後は年に1回、iDeCo+の実施条件を満たしているか現況届の提出が必要です。
iDeCo+は導入にコストがかからない福利厚生制度
iDeCo+を導入するにあたって、導入コストはかかりません。似たような制度として企業型確定拠出年金がありますが、こちらは導入コストがかかりますし、運営管理機関を決定したり投資教育が必要だったり、会社の責任は大きいです。
企業型確定拠出年金を導入するほどの余裕はないけれど、福利厚生を充実させたいのであればiDeCo+は選択肢の1つとなり得るでしょう。iDeCo自身が老後資産形成に優れた制度です。それを会社として応援するiDeCo+は従業員にとってもありがたい制度となるはずです。
出典
(※)iDeCo公式サイト「中小事業主掛金納付制度(愛称「iDeCo +」(イデコプラス))の届出書」
執筆者:前田菜緒
FPオフィス And Asset 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2019年FP協会広報スタッフ