ふるさと納税は本当にお得?仕組みと返礼品を最大限活用するコツ
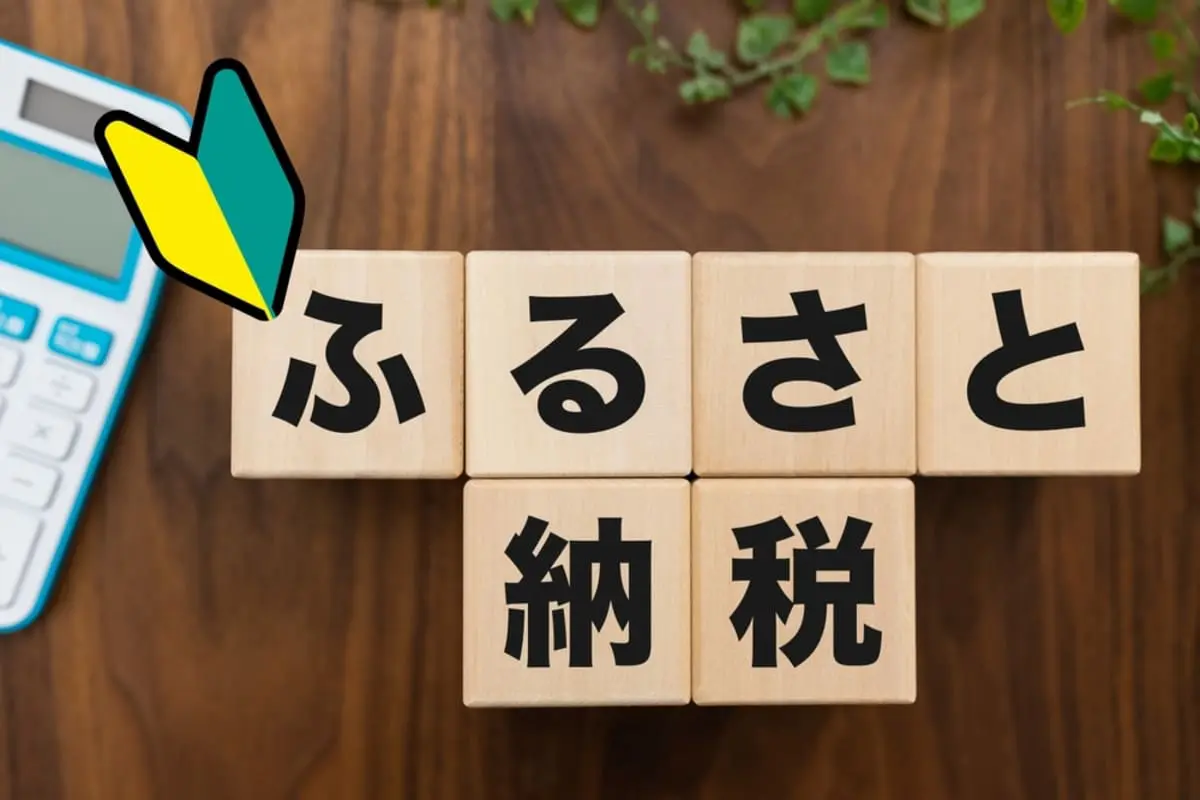

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
ふるさと納税はいつから始まった?
ふるさと納税は、2006年に福井県知事の西川一誠氏が発案した制度といわれています。同氏の発案をきっかけに、国会でも議論され、2007年6月1日に菅義偉氏の主導のもと、総務省がふるさと納税制度の創設に向けて「ふるさと納税研究会」を立ち上げました。
そして、2008年4月30日にふるさと納税を盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法律案」が衆議院で可決され、翌月の5月からふるさと納税制度が始まりました。
ふるさと納税の制度が導入された理由
ふるさと納税が生まれた背景をご存じでしょうか。
現代では、多くの人が地方で生まれた育った後、進学や就職を機に都会に移り住む傾向があります。地元の自治体で医療や教育などのサービスを受けて育った人々が、税金を納める頃にはその地を離れてしまうため、都会の自治体は税収を得る一方で、地方の自治体には税収が入らない状況が生まれています。
この問題を解決するために、ふるさと納税制度が設けられました。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は「納税」と名がついていますが、実際には自分の選んだ自治体へ「寄付」ができる制度です。選んだ自治体に寄付することで、所得税や住民税が控除されます。
控除を受けられる上限は、給与収入や扶養家族の人数などによって決まります。しかし、控除される金額は上限に関係なく、寄付金の総額から2000円差し引いた金額です。例えば、5万円寄付した場合には、5万円−2000円=4万8000円が控除される仕組みです。
つまり、ふるさと納税を最大限活用して控除を受けるためには、少額の申し込みではなく、自身の控除を受けられる上限額にできるだけ近い金額まで申し込み、返礼品を受け取るようにしましょう。
なお「控除の上限額が分からない」という方は、ふるさと納税サイトなどでシミュレーションができるため、利用してみるとよいでしょう。
実際にふるさと納税を申し込んでみましょう
ふるさと納税の申込手順や、寄付金控除の方法について解説します。
ふるさと納税の申し込み3ステップ
ふるさと納税は、次の手順で申し込みをして控除を受けましょう。
(1)控除額を確認し、いくら利用できるかを把握する
(2)ふるさと納税の申し込みサイトで自治体および返礼品を選んで申し込む
(3)寄附金控除の申し込み手続きをする
寄付金控除の申し込み方法
ふるさと納税で寄付した金額の控除を受けるためには、ふるさと納税への申し込みだけではなく、寄附金控除の申し込みが必須です。申込方法は「確定申告」もしくは「ワンストップ特例制度」で行います。
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者が利用できる制度です。制度を利用するには、申し込んだ自治体が年間で5ヶ所以内である必要があります。
自営業者や年収2000万円以上の高所得者、不動産所得がある場合、確定申告が必須となり、ワンストップ特例制度は適用されません。また住宅ローン控除や医療費控除を受ける場合も、確定申告が必要です。
確定申告をしなくても、申請書を申し込んだ自治体に送るだけで控除手続きが完了するため、会社員で確定申告する必要のない方には、こちらの制度の利用がおすすめです。さらに自治体によっては、マイナンバーカードがあれば、オンラインで申請が完了する場合もあります。
納めたお金はどうやって使われるの?
ふるさと納税をすると、食べ物や家電などさまざまな返礼品を受け取れることは、テレビなどでも紹介されているためご存じの方も多いでしょう。しかし、寄付した全額が返礼品にあてられるわけではありません。
寄付額の上限30%までの選んだ品物が返礼品として受け取れます。残りの使い道は、諸経費のほか、自治体の活性化などに利用されます。使い道は申し込み時に選択できるため、何に役立ててほしいかは、申し込みをした方が選択可能です。
ふるさと納税を活用して地元に貢献を
ふるさと納税は、生まれ育った地域をはじめ、選んだ自治体に貢献できるだけでなく、寄付した金額の30%までの返礼品を受け取れるお得な制度です。申し込んだ後は、確定申告やワンストップ特例制度での申請を忘れず、控除を受けましょう。
また、近年では返礼品に注目が集まりがちですが、本来の目的は「生まれ育った地元への貢献」です。一度、自分の生まれ故郷への寄付も検討してみてはいかがでしょうか。
出典
総務省|よくわかる!ふるさと納税|よくわかる!ふるさと納税
総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

































