年金を「月14万円」受給中。「確定申告」は不要だと思ってたけど、したほうが良い場合もあるの?
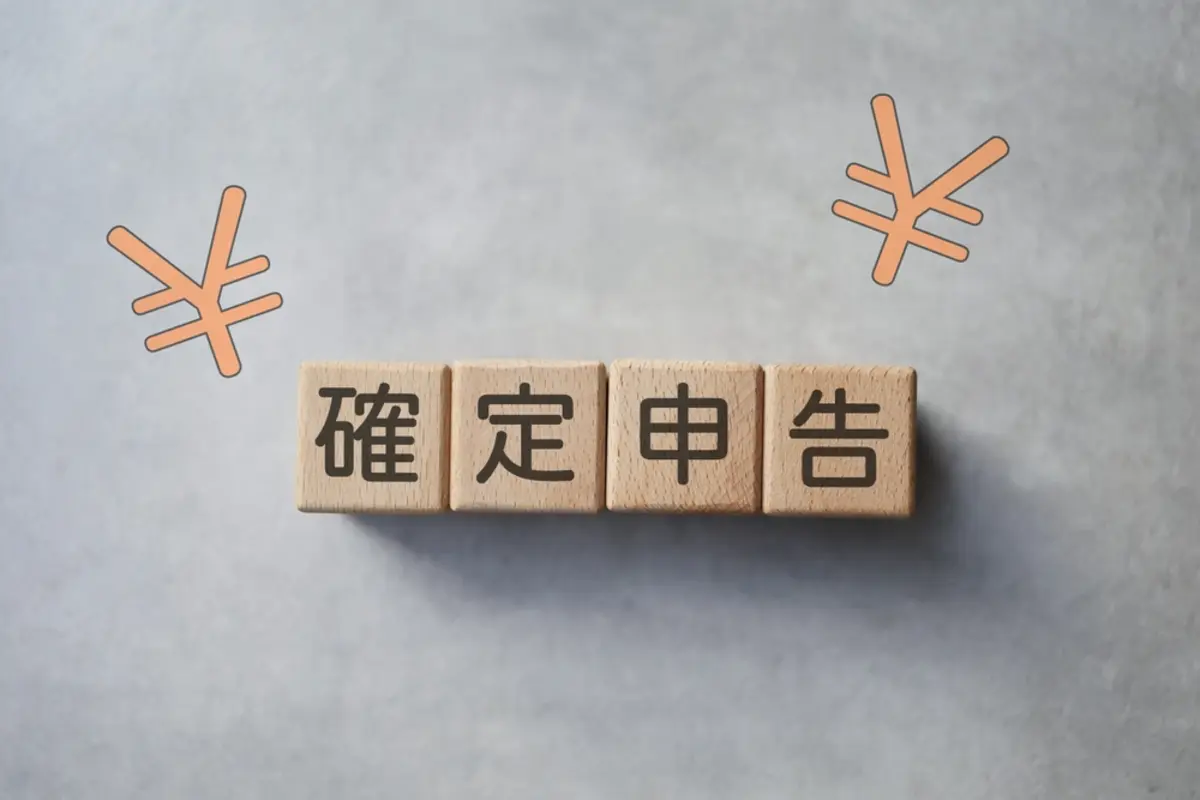
本記事では、年金受給者の確定申告について詳しく解説し、「確定申告をしたほうが良いケース」をわかりやすく紹介します。自分にとって確定申告が必要かどうか、ぜひ確認してみてください。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
年金受給者の確定申告について
国民年金や厚生年金といった公的年金は、「雑所得」に分類されます。そして、年金収入が年間400万円以下であり、さらに公的年金以外の所得が20万円以下の場合は「確定申告不要制度」が適用され、確定申告を提出する必要はありません。
年金収入が400万円を超える場合や、アルバイト収入などの副収入が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
年金受給者で確定申告したほうがいい場合
年金受給者で確定申告したほうがいい場合は、主に以下の5つです。
・高額な医療費を支払った
・生命保険料を支払っている
・住宅ローンを支払っている
・災害や盗難にあった
・ふるさと納税をした
これらの条件に該当する場合、確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能性があります。少しの手間で大きなメリットが得られる場合があるため、必要な書類をしっかり準備して確定申告に臨みましょう。
高額な医療費を支払った
年間の医療費が10万円を超える場合、10万円を超えた分が医療費控除の対象になります。ただし、年収が200万円未満の人の場合、総所得金額等の5%を超える医療費が控除対象です。
現役時代に医療費控除を申請した経験がある人の中には、「医療費が10万円を超えないと対象にならない」と記憶している人も多いでしょう。しかし、年金生活者の場合、多くは「所得が200万円未満」に該当します。
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の受給者は1572万3841人で平均月額は14万7360円、国民年金の受給者数は3305万6697人で平均月額は5万7700円となっています。年収換算すると、下記の通りです。
厚生年金:14万7360円×12ヶ月=176万8320円
国民年金:5万7700円×12ヶ月=69万2400円
この場合、医療費が「所得の5%」を超えると医療費控除が適用されます。例えば、所得が140万円の場合、医療費が7万円を超えた時点で控除を受けることが可能です。頻繁に病院を利用する人は、領収書をきちんと保管しておきましょう。
生命保険料を支払っている
生命保険料を支払っている場合は、生命保険料控除を受けることが可能です。控除金額が大きいことから、見逃すと大きな損失につながる可能性があります。適切に申告することで負担を軽減できるため、必ず手続きを行いましょう。
住宅ローンを支払っている
10年以上の住宅ローンを利用して取得やリフォームを行うと、ローン残高の0.7%が取得は13年間、リフォームは10年間にわたり所得税から控除されます。リフォームの場合、控除対象となる借入金の上限は2000万円で、最大で年間14万円、10年間で合計140万円の控除が可能です。
また、所得税から控除しきれない分は、住民税の一部から差し引かれる仕組みになっています。
災害や盗難にあった
災害や盗難などによる被害を受けた場合、雑損控除の対象となることがあります。この際に発生した支出については、証拠となる領収書をしっかり保管しておくことが大切です。
ふるさと納税をした
年金を受給している人でも、所得税や住民税を納めていれば、ふるさと納税による控除を受けることができます。
ただし、公的年金の収入が65歳以上で158万円以下の場合は控除が受けられず、全額自己負担になってしまうので注意しましょうまた、ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税した場合は、確定申告は不要です。
「月14万円の年金収入」の場合でも、確定申告で税金が還付される可能性がある
「月14万円の年金収入」の場合でも、特定の条件に該当すれば、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。高額な医療費や生命保険料の支払い、住宅ローン、災害や盗難、ふるさと納税といった特定の条件に該当する場合、確定申告を行うことで税金の還付を受けられるかもしれません。
医療費控除については、年収が200万円未満の場合、「所得の5%を超える医療費」が対象となるため、年金生活者には該当するケースが多いです。また、生命保険料控除や住宅ローン控除を適用できる場合、適切に申告することで家計負担を大きく軽減できる可能性があります。
税負担を最小限に抑えるためには、自分が該当する条件に当てはまるかどうかを確認しましょう。日頃から医療費や保険料の領収書、災害や盗難時の証明書など、必要な書類をしっかりと保管しておくことが重要です。
出典
国税局 公的年金等を受給されている方へ
厚生労働省 令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
































