歯の矯正で今年「60万円」支払いました。確定申告でいくらくらい戻ってきますか?
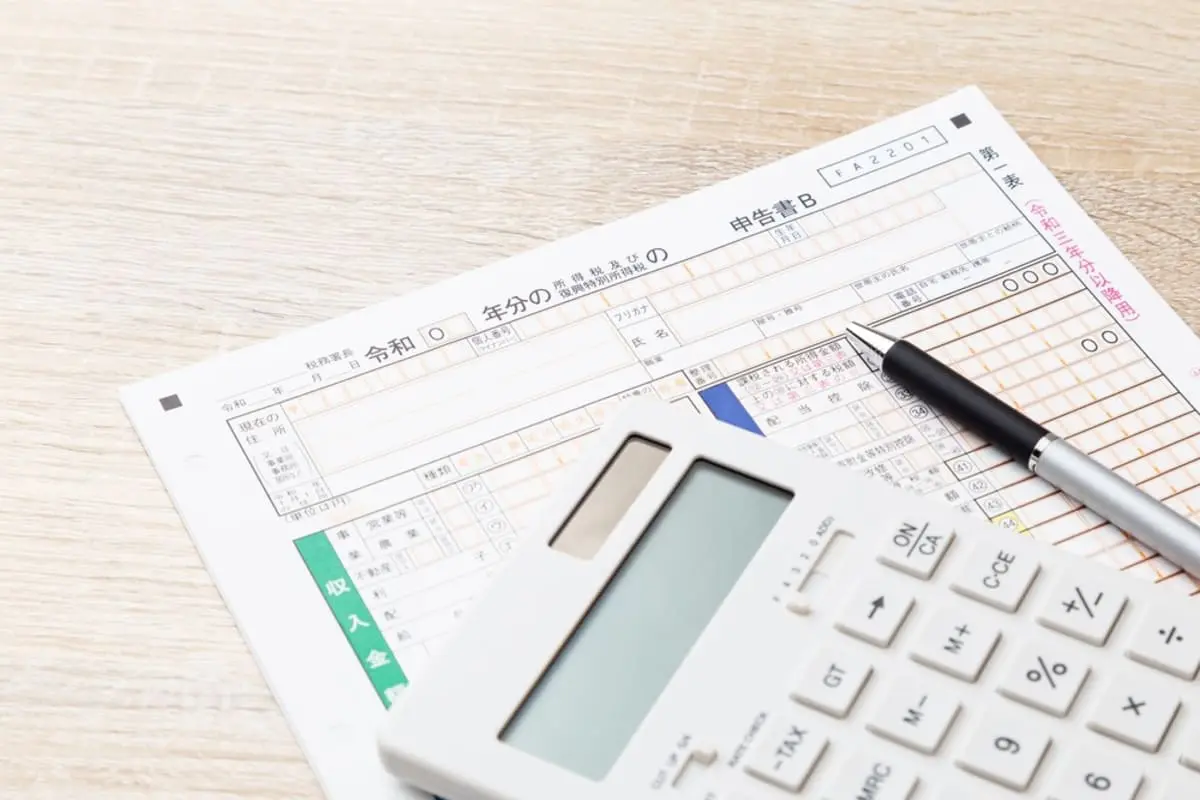
今回は、歯の矯正で税金が戻ってくる医療費控除の概要や、60万円を支払った場合に還付される金額について調べてみました。医療費控除を利用する際の注意点もご紹介しますので、参考にしてください。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
歯の矯正で税金が戻ってくる? 医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、自分と自分の家族が支払った医療費の総額が10万円を超える場合に、確定申告で所得税の一部が還付される制度のことです。
医療費控除の対象となるのは、納税者が自分または自分と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費です。またその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費である必要があります。
医療費控除には、歯の治療にかかった費用も含まれます。歯の矯正の場合は、「歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用」が対象になるようです。
同じ歯科矯正治療でも「容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用」は対象になりません。つまり、将来の就職や結婚を考慮して歯の矯正をする場合は対象外である点に注意が必要です。
歯の矯正で60万円支払った場合に還付される金額は?
医療費控除の対象となる歯の矯正を行って、治療費として60万円支払った場合、確定申告をするといくら還付されるのか気になるでしょう。医療費控除の対象となる金額(最高200万円)は以下の式で計算します。
・実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)
歯の矯正で60万円支払った場合、それ以外の医療費がなく保険金などで補てんされる金額が0円であれば、医療費控除額は50万円です。還付金の計算は、医療費控除対象額に所得税率を掛けて計算します。所得税率は課税される所得金額を基に5%~45%に設定されています。つまり所得金額に応じて2万5000円~22万5000円が還付される計算です。
これはあくまでも歯科矯正にかかった治療費だけで、保険金などで補てんされる金額が0円の場合を想定しており、実際はそのほかの医療費も含めた総額で計算します。
歯の矯正で医療費控除を利用する際の注意点
歯の矯正で医療費控除を利用する際は、以下の点に注意が必要です。
●セルフメディケーション税制との併用はできない
●ふるさと納税のワンストップ特例を適用できなくなる
セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種を受けるなど一定の取り組みを行っている居住者で、ドラッグストアで購入できる医薬品など特定一般用医薬品等購入費が一定額を超えた場合に所得控除が受けられる制度です。同年に両方を併用することはできず、いずれかを選択した場合に後から変更できない点にも注意が必要です。
ふるさと納税を利用している場合は、確定申告が不要になるワンストップ特例を申請している人もいるでしょう。しかし医療費控除を受けるために確定申告をする場合は、ワンストップ特例を適用できなくなります。医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合は、ふるさと納税の全額についても所得税の確定申告を行う必要が生じます。
歯の矯正で60万円を支払った場合の還付金は医療費控除対象額に所得税率を掛けて算出できる
歯の矯正で60万円を支払った場合、医療費控除の対象となる金額を計算して、所得税率を掛けて目安を知ることが可能です。
例えばその年の医療費の総額が60万円で、保険金などで補てんされる金額が0円、総所得金額等が200万円以上であれば、医療費控除対象額は50万円です。これに所得税率5%~45%を掛けると、所得金額に応じて2万5000円~22万5000円が還付されることになります。
実際に還付される金額は、歯の矯正だけでなくそれ以外の医療費の総額であることや医療費控除対象額の計算、総所得金額および所得税率などによって異なります。また審美目的の矯正では医療費控除の対象外になることやセルフメディケーション税制との併用ができないことなどにも注意が必要です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
































