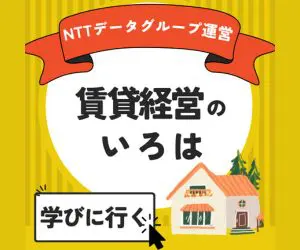「アパート」を建てるのが「節税」になるって本当? 親が「相続税対策だ」と言っていますが、借金をしてまでやることなのでしょうか?
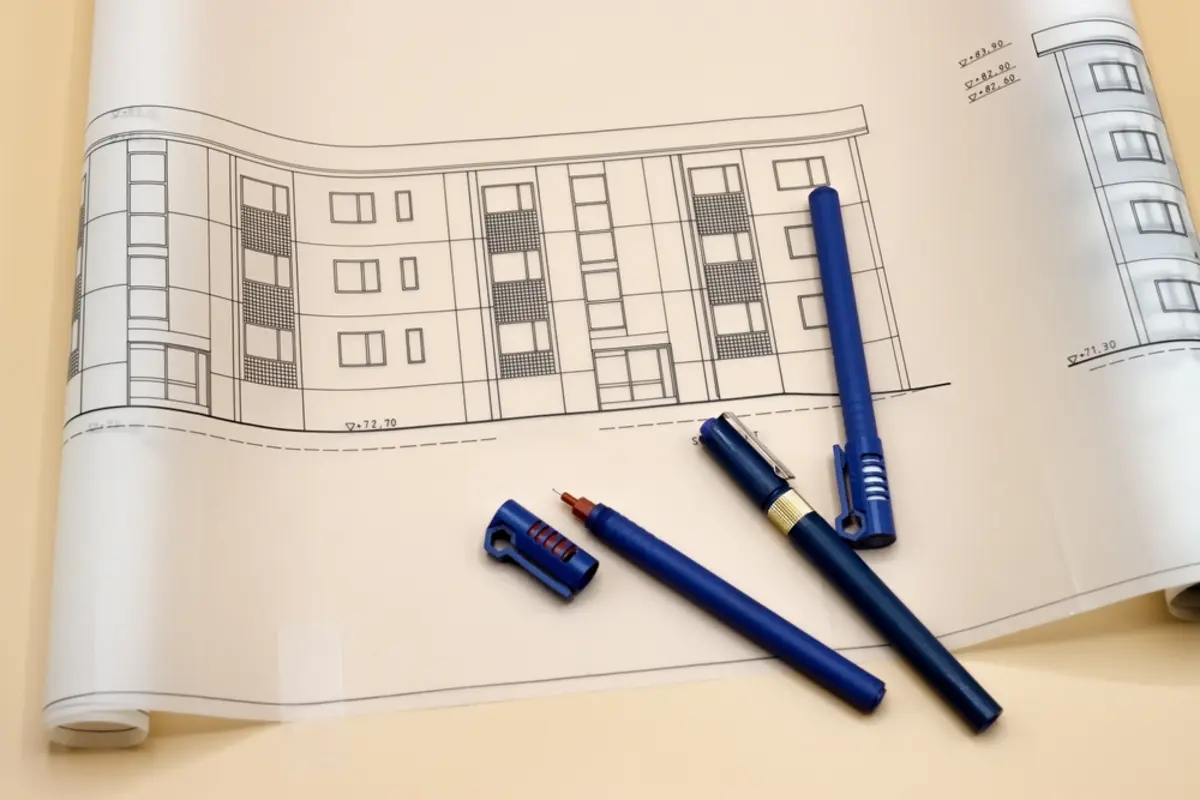
本記事では、土地に賃貸物件を建設することが相続税対策につながる理由を解説するとともに、借金をしてアパートを建てる場合のシミュレーションを紹介します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
土地活用を検討するなら
無料査定実施中! 公式サイトを見る
アパートを建てると相続税対策になる理由
不動産の相続税評価額は、条件次第でさまざまな減額が認められています。そのひとつが、不動産を第三者に貸していることです。
建物や土地など、第三者に貸している不動産は、自分の居住用として所有している物件と比べて自由度が下がります。そのため、第三者に貸している不動産は、権利を貸している割合(借地権割合・借家権割合)に応じて、相続税評価額を減額することが認められています。
アパートやマンションなど、第三者に貸すための建物がある土地は「貸家建付地」といい、相続税評価額を減額する対象です。
また、小規模宅地等の特例により、貸付事業用の宅地等は200平方メートルを限度として、相続税の課税価格に算入する金額が50%減額されます。そのため、アパートの建設は、土地の相続税対策につながります。
貸家建付地の相続税評価額の計算方法
貸家建付地の相続税評価額は、次の式で計算します。
自用地としての価額−(自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
借地権割合は地域ごとに30〜90%の間で定められており、通常は土地の利用価値に応じて割合が高まります。一方、借家権割合は都道府県ごとに定められており、国税庁のホームページでも確認することが可能です。
また、貸家建付地の相続税評価額の計算では「賃貸割合」を考慮する必要があります。
賃貸割合とは、賃貸用物件の専有部分の床面積に対して、実際に貸し出されている専有部分の床面積の割合を表すものです。例えば、物件全体の床面積が300平方メートル、実際に貸し出している部屋の床面積の合計が180平方メートルの場合、賃貸割合は180÷300×100=60%となります。
なお、賃貸物件を建てる場合は、その物件も相続の対象です。貸家建付地(土地)とは別に、建物の相続税評価額は次の式で計算します。
固定資産税評価額−(固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)
土地活用を検討するなら
無料査定実施中! 公式サイトを見る
相続税対策の賃貸アパート建設、借金してまでやるべき?
相続税対策のため賃貸アパートは借金してでも建てるべきなのか、実際にシミュレーションしてみましょう。
● 土地の相続税評価額:1億円
● 賃貸アパートの建築費用6000万円を借金
● 借地権割合:70%
● 借家家割合:30%
● 賃貸割合:100%
この場合、土地の相続税評価額の計算結果は以下の通りです。
1億円−(1億円×0.7×0.3×1)=7900万円
もし、土地の全面積に小規模宅地等の特例が適用されるとすると、この評価額からさらに50%減額されます。その場合、土地の相続税評価額は以下の通りです。
7900円×0.5=3950万円
新築物件の固定資産税評価額は、建築費用の60%とされています。そのため、アパート本体の固定資産税評価額は6000万円×0.6=3600万円とし、以下の通り計算します。
3600万円−(3600万円×0.3×1)=2520万円
3950万円+2520万円−6000万円=470万円となり、相続税評価額はもとの金額から大幅に減額されました。
ただし、これはあくまで建築費用の借金(負債)6000万円を、そのまま相続したと仮定した場合です。被相続人の生前に借金の返済が進んだ場合は、節税効果が薄れてしまいます。
また、近年は物件の空室率に悩むオーナーも多く、相続税を減らせたとしても、物件の管理・維持費で赤字になってしまうケースも少なくありません。
相続税対策としての賃貸アパート建設は、こうしたリスクも十分考慮したうえで検討する必要があるでしょう。
リスク・リターンが見合っているか判断することが重要
賃貸アパートが建つ土地は貸家建付地とみなされ、相続税評価額の減額対象です。また、小規模宅地等の特例により、土地の相続税の課税価額の減額も認められています。
しかし、賃貸アパートは建てて終わりではなく、建物の管理・維持や入居者集めなど、賃貸経営にまつわる負担はどうしても生じてしまいます。リスクとリターンを総合的に判断したうえで、賃貸アパートの建設を検討しましょう。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4614 貸家建付地の評価
国税庁 No.4602 土地家屋の評価
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
土地活用を検討するなら
無料査定実施中! 公式サイトを見る